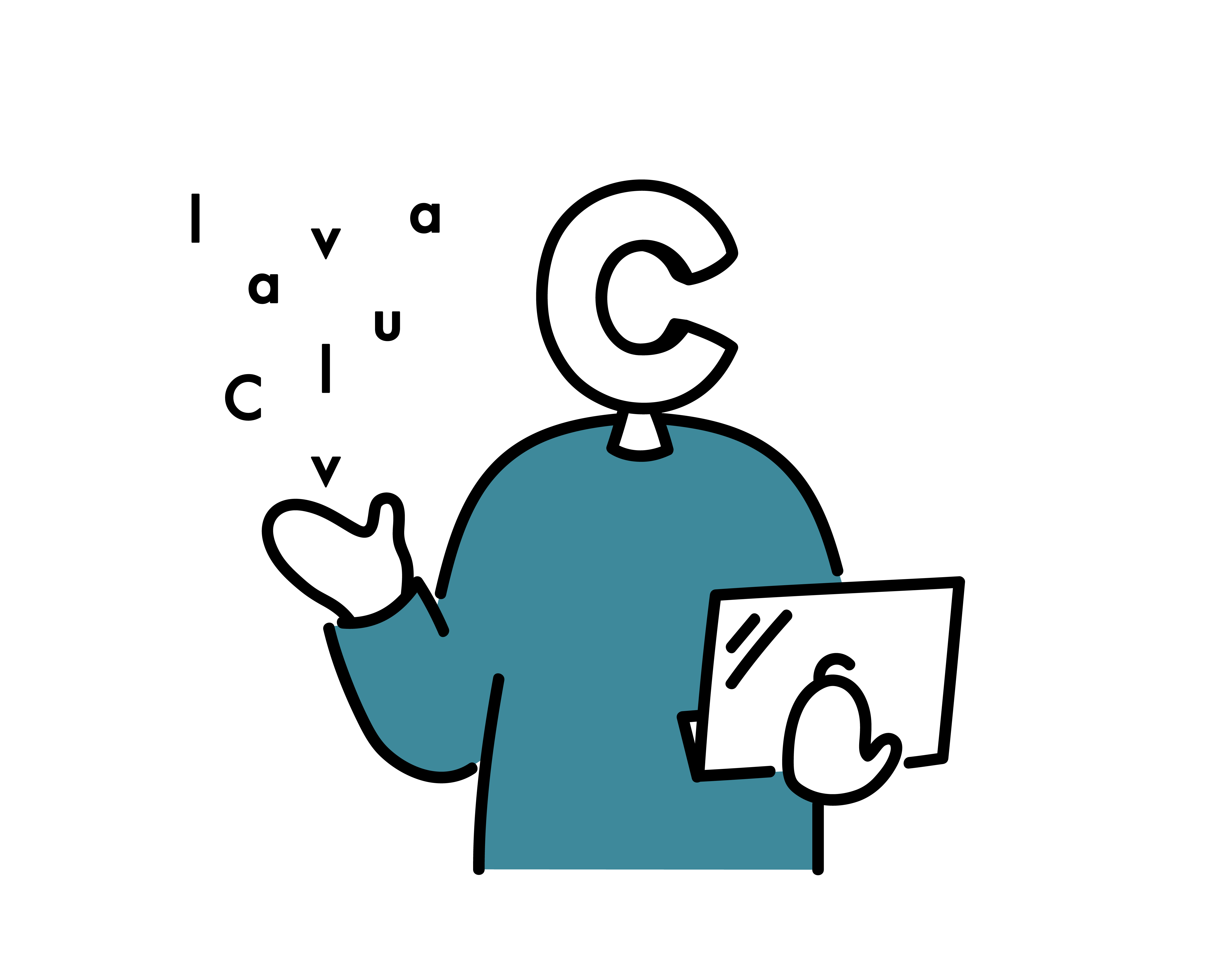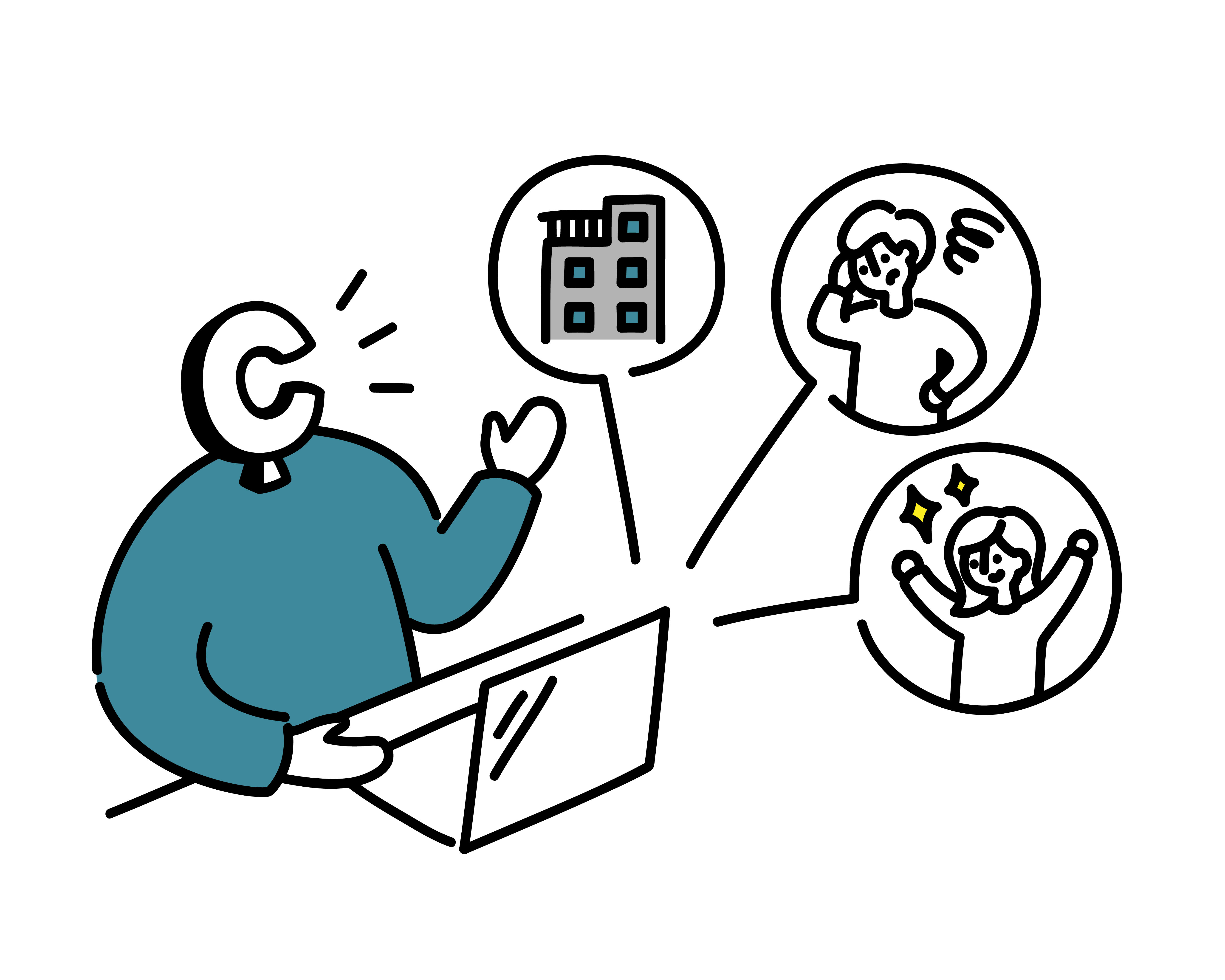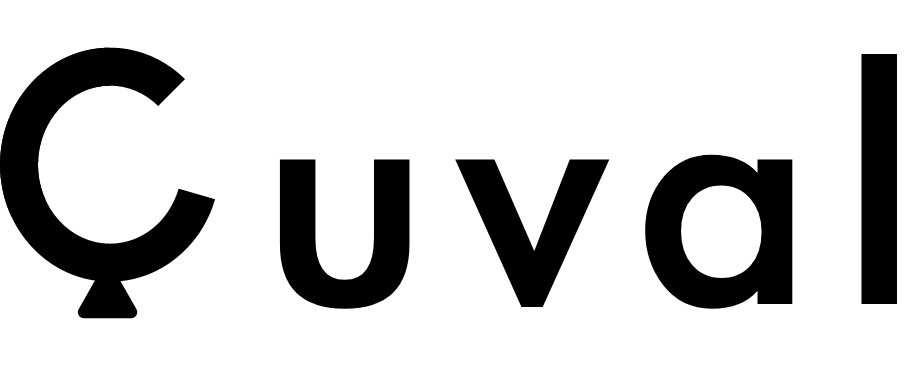林 正悟氏|nocall株式会社 Co-Founder, 代表取締役CEO
広島県福山市出身。高校卒業後に渡米し、アメリカの大学で教育心理学を専攻。帰国後は広島県のインターナショナルスクール設立プロジェクトに参画し、7校の立ち上げ支援に関わる。2020年にnocall株式会社を創業。現在は、生成AIを活用した電話代替サービス「nocall.ai」を展開し、社会課題とテクノロジーの接点で新たな価値創造に挑む。
nocall株式会社について
── 御社の事業内容を教えて下さい。
nocall株式会社では、生成AIを活用した電話サービス「nocall.ai」を提供しています。ChatGPTなどに代表される大規模言語モデル(LLM)を活用し、電話に特化したAIとしては国内初の取り組みです。また、SaaS型パッケージとして提供している生成AI電話サービスとしては、現時点では日本で唯一の事例だと思います。
主に社員数100〜1000名規模の企業様に導入いただいており、リマインド連絡やヒアリング、掘り起こし営業など、従来は人が行っていた電話発信業務をAIが完全に代替しています。
まさに「ChatGPTのような巨人の肩に乗る」ことで実現した、生成AI時代ならではの実用的なプロダクトだと考えています。
林さんのキャリア
── 幼少期に、今のキャリアに繋がるような経験があれば教えてください。
小学校4〜5年生くらいまでは、「人生のピークだったな」と思っています(笑)。広島県福山市の出身で、実家はもともと福山藩の南側を治めていた庄屋だったらしく、それを誇りに感じていました。戦後、GHQによって土地を失って以降は、親族の多くが医師や歯科医になり、自分もその一員として見られていました。
そんな中で、自分がアメリカの大学に進学するというのは、家族の中ではかなりアウトライヤーな選択でした。きっかけのひとつは、小学4〜5年生の頃に曽祖母が亡くなったことです。90代だったので受け入れられたものの、「人は本当に死ぬんだ」と目の前で感じたことで、「死ぬまでに何をするべきか」と強く考えるようになりました。
それからは、周囲と同じように楽しむことが難しくなり、常に「自分は何のために生きるのか」と考えるようになっていきました。
祖父が歴史好きだった影響で、大河ドラマを一緒に観たり、司馬遼太郎の本を読んだりして、幕末の志士たちの生き様に強く惹かれるようになりました。「現代でこんなふうに生きることは難しい」と思っていたところ、中学生の頃にスティーブ・ジョブズの伝記を読み、起業家という生き方に出会いました。
「起業家って、現代の志士みたいな存在かもしれない」と感じ、孫正義さんの本や『竜馬がゆく』なども読み漁り、「スティーブ・ジョブズもアメリカだったし、自分もアメリカに行こう」と、アメリカの大学進学を決意しました。
── ご家族から反対はありませんでしたか?
めちゃくちゃ反対されました(笑)。特に母親からは、「みんなが必死で受験勉強しているのに、逃げるのか」と言われました。当時、自宅にはインターネットもなかったので、図書館でひたすら情報収集をして、海外大学の資料請求をしまくりました。
中学卒業後すぐに高卒認定試験を受けて、合格後は「もう高校卒業と同じだから、大学に行きたい」と母に伝えましたが、「そんなのありえない」と一蹴されてしまって。そこからの3年間は、ひたすら英語の勉強に打ち込み、自分の本気度を行動で見せていきました。最終的にはようやく「そこまで本気なら行ってもいい」と認めてもらえました。
── では、実際に渡米されてからはどのようなことを学ばれたのでしょうか?
起業したいという想いは持っていたものの、当時はまだテーマが定まっていなかったので、特定の分野を決め打ちで学ぶよりも、幅広く学べる「リベラルアーツ」の環境が自分に合っていると感じていました。そういった背景もあって、紹介してもらったアメリカの大学に進学しました。
入学後もしばらくは専攻が決まらず、最初は経営学を履修していたのですが、全く面白く感じられなかったんです。自分は「経営者になりたい」というより「起業家になりたい」タイプなので、既存の仕組みを回すための学問にはあまり惹かれませんでした。
むしろ、ゼロから何かを生み出すプロセスにこそ興味があったんですよね。
── 授業自体は面白かったと伺いました。
そうなんです。とにかく、教育環境が自由で柔軟なんですよ。自分の関心に応じて授業を選べるという仕組みにすごく感動しました。日本の教育とはまったく違っていて、「これが本当のリベラルアーツなんだ」と思いました。
日本だと「リベラルアーツ=広く浅く学ぶ」みたいなイメージがありますが、アメリカでは本当に“自分で選んで学んでいる”という実感が持てました。こういった教育が日本にはなぜないのか?と疑問を持ったのが、教育分野に興味を持つきっかけになったと思います。
── そこから心理学系の専攻に進まれたのですね。
はい。人間にポジティブな影響を与えるにはどうすればいいのか──学力などの能力面だけでなく、感情やモチベーションといったエモーショナルな面も含めて、そういったことを深く学びたいと思うようになり、自然と教育心理学の方向に進んでいきました。
── 大学卒業後のキャリアについて伺います。広島県のインターナショナルスクールのプロジェクトには、どのような経緯で参画されたのでしょうか?
たしか大学3年生の頃だったと思いますが、インターナショナルスクールを立ち上げようとしていた末松 弥奈子さんという社長をある経済界の方からご紹介いただいたのがきっかけです。
もともと教育系のプロジェクトに興味があると話していたこともあり、大学在学中からサマースクールなどのお手伝いをさせていただいていました。卒業後もそのまま、開校に向けて本格的に動き出すプロジェクトに正社員として参画することになりました。
── 実際にどのような業務を担当されていたのでしょうか?
入社した当初、現地には自分以外ほとんど人がいない状態でした。社長の運転手の方と、リモートの上司とで、現場は実質ひとり。
事業計画の作成、サマースクールのオペレーションなど、ゼロからの立ち上げのあらゆる業務をやりました。現地のオペレーションまで、とにかく何でもやっていましたね。
── すごいですね。それだけ大きな裁量を任されていたのはなぜでしょうか?
「好きにやっていいよ」と社長に任せてもらえたおかげです。若かったこともあって、やることすべてが新鮮で楽しかったですし、裁量が大きい分、責任感とやりがいも感じていました。
大学を卒業したばかりの22歳の若造に、数百億円規模のプロジェクトを任せてもらえたわけですから。もともとこの学校は、造船系の財閥が母体で、建築・保険・運営に必要なリソースがグループ内にすべて揃っていたことも大きかったです。
── プロジェクトを通して得られたものは何だったと思いますか?
一番は調整力だと思います。現場には多くのステークホルダーがいて、それぞれの立場や思惑も異なります。若い自分が中心になって動かすうえで、相手のニーズを丁寧にくみ取り、こちらの目的と調和させながら着地させていく必要がありました。
この経験は、その後の起業や組織運営にも大いに活きていると思います。
── その後、2020年に学校が開校したそうですが、その後の動きについても教えてください。
開校したタイミングで、自分の担当する“立ち上げフェーズ”の仕事が一段落したんです。そこで「そろそろ自分の事業を始めようかな」と考えるようになりました。
ただ、ここを離れた直後から別のインター設立プロジェクト──イギリスの有名校の日本進出支援の依頼も受け、この立ち上げで得た経験を生かす機会に恵まれました。具体的には、日本の企業とイギリス本校を繋いでアライアンスを組み、日本校を立ち上げるというプロジェクトでした。
nocall株式会社 創業後
── 創業後、最初はどのようなかたちで事業をスタートされたのでしょうか?
2020年12月の創業当初は、社会人向けの教育サービスを展開していました。もともと高価格帯の教育プログラムに関わっていたこともあり、もっと広く社会人教育にアプローチしたいという思いが強く、それをEdTechのかたちで実現したいと考えていたんです。
最初の取り組みは、いわゆる『リーンスタートアップ』の教科書的アプローチに従って、ユーザー検証を重ねながら、ひたすら愚直にサービスづくりを進めていくというものでした。
ちょうどその頃はコロナ禍が始まったタイミングで、オンライン教育への注目度が急速に高まっていた時期でした。インドのEdTech企業がサッカーワールドカップのスポンサーを務めるような動きもあり、日本でもUdemyなどのプラットフォームが注目を集めていました。
とはいえ、実際には「購入して満足して終わる」というケースが多く、受講終了率はわずか5%程度というデータもありました。そこで私たちは、購入者同士がグループを組んで教え合える仕組みを導入することで、学習の継続率が上がり、結果としてLTV(顧客生涯価値)も伸ばせるのではないかと考えたんです。
── 開発はどのように進めていったのですか?
最初はプロトタイプすらない状態で、コンセプトベースの無料サービスとして立ち上げました。実際に人が集まり始めたことで「これはいけるな」と確信し、有料化に踏み切ってから裏側のシステムを開発していきました。
教育ビジネスの本質は、やはりレピュテーション(評判)にあると思っています。卒業生が実際にキャリアへと繋げていくことで、実績が可視化され、サービスへの信頼も広がっていく。実際、受講してくれた多くの方がデータサイエンス分野の仕事に就くなど、しっかり成果も出ていたと思います。
── 非常に好調なスタートに見えますが、なぜピボットを決断されたのでしょうか?
悪くはなかったんですが、短期間で急成長するような事業ではないなという実感がありました。さらに当時の自分には、「TAM」といった市場のポテンシャルに関する視点がまったくなかったんです。とにかく、ユーザーの声に愚直に応えていくというスタンスで進めていました。
でも実際に資金調達フェーズに入ってみると、EdTechという領域の評価が極端に低く、どこの投資家もなかなか取り合ってくれないという現実に直面しました。
── 具体的に、どのような壁にぶつかったのでしょうか?
たとえば、月の継続率80%という成果を出していたにもかかわらず、「今のEdTechは、投資対象としては厳しい」と言われてしまったんです。実績があっても、市場そのものへの期待値が低いと、なかなか資金は集まらない。それが大きな壁でした。
そんななかで参加したIVS(Infinity Ventures Summit)で、Skyland Venturesの木下さんと出会ったんです。木下さんからは「事業としては厳しそうだけど、人として面白いから、うちのオフィスに遊びにおいでよ」と声をかけてもらって。それが、ピボットの大きなきっかけになりました。
── オフィスに通うようになってから、どのような変化があったのでしょうか?
最初は週1回通うつもりだったのが、いつの間にか週3くらいで通ってました(笑)。木下さんの隣で、投資家が案件をどう見るかとか、他の起業家がどう壁打ちしているかを間近で見るようになって、自分の視点も大きく変わっていったんです。
木下さんにご紹介いただいたエンジェル投資家や上場企業社長方から事業の可能性についてのフィードバックをいただく中で、最終的には自分自身も納得感を持って、腹をくくってピボットを決断しました。
── そこから、現在の事業につながる動きが始まったんですね。
はい。新しい事業案をまとめて、Skyland Venturesなどから資金調達を実現できました。それが2023年の9月頃です。
ちょうどその時期、Skylandが運営していたインキュベーションプログラムで出会ったのが、CTOの森本です自分と似たようなアイデアを持っていて。「それなら一緒にやろうよ」と意気投合しました。
森本が開発を担当し、約2ヶ月でベータ版を完成させてくれて、2023年12月に正式ローンチ。そこから半年ほどで有料化し、クライアントも順調に増えて、現在に至ります。
── 現在のサービスについて、セールス面ではどのように展開されてきたのでしょうか?
実は、「セールスで苦労するようなプロダクトだったら最初からやらない」と決めていたんです。
── それは創業当初からの方針だったのですか?
はい。雑にリリースしても自然と問い合わせが来るようなプロダクトでなければ、将来性が低いと思っていました。売るのに苦労する時点で、プロダクトとしてはまだ不十分だと考えるようにしていたんです。
なので、最初にプレスリリースでコンセプトを出したとき、どれくらい反応があるかを一つの判断基準にしました。結果的に多くの問い合わせをいただけたので、「これはいける」と確信することができました。
── 実際には、どのようなかたちで営業活動を進めているのでしょうか?
ほとんどしていないんですよ(笑)。公式サイトを開設して、PR TIMESで機能追加のお知らせを出す程度です。それでも、社員数100〜1000名規模の企業からコンスタントに問い合わせがあり、営業をかけずとも受注につながっているのが現状です。
── それは非常に大きな強みですね。
そうですね。やはり、社会的なニーズとプロダクトのタイミングがガチッと噛み合っていることが、今の事業の最大の強みだと思っています。
── 林さんの目線で、現在の事業の魅力をどう捉えていますか?
やっぱり一番の魅力は、シンプルに「ワクワクする」ことですね。生成AIという新しい技術が生まれて、今まさにその技術が社会課題と直結するかたちで使われようとしている。この瞬間に立ち会えていること自体が、すごくエキサイティングなんです。
特に日本では、人口減少による労働力不足という問題が年々深刻になっていて、「これ、どうやっても解決できないんじゃないか」と感じるような状況がある。その中で、「だったら労働はAIに任せてしまえばいい」という技術が実際に現れた。そして、それがちょうど世の中の課題とガッチリ噛み合っている。
いまはまさに、「巨大な課題」と「圧倒的な技術的ソリューション」が揃った状態なんです。そうした背景のなかで、私たちはそのど真ん中を走っている。しかも、プロダクトを1丁目1番地から作って、実際に世の中で使われている。そういう状況にいられることが、何より面白いですし、本当にやりがいを感じます。
── 林さんご自身は、現在どのような業務に時間を割かれていますか?
私の業務内容は、だいたい3ヶ月ごとにバランスが変わっていくのですが、現在では、主に採用に3割、カスタマーサクセスに5割ほどの時間を使っています。開発まわりには1割程度、残りはセールスや経営全般といったその他の業務に充てている状況です。
── 今後、特に注力していきたい領域はありますか?
はい。カスタマーサクセスについては、最近2名体制に強化したばかりなので、今後は私自身の関与を少しずつ減らしていけると考えています。その分、今後は経営やセールスにもう少しリソースを割いていきたいですね。
今までは「入ってくる問い合わせに対応するだけで手一杯」という状態なので、より戦略的なセールス展開や、新しいユースケースの開拓にも力を入れていきたいと思っています。
現在の組織について
── 組織としての魅力や、逆に課題と感じていることはありますか?
魅力は、とにかく「いいやつ」が多いことです(笑)。能力はもちろんですが、「この人が困っていたら助けたくなるか?」という観点で採用しているので、雇用形態に関係なく、チームの雰囲気がすごく良い。
自然と助け合いの文化が生まれていて、信頼の循環ができている。これは、今のnocallの大きな強みだと思っています。
── 一方で、課題は?
やっぱり、若い組織なので荒削りな部分があるのは否めないです。
最年長はCOOの阿部が32歳、CTOの森本は26歳くらいですし、インターンの中にも実質フルコミットで月146時間働いているようなメンバーがいて、もはや社員同然です。
その分エネルギーはあるんですが、体制としてはまだ未成熟な部分が残っているのも事実ですね。
── “いいやつ”というキーワードが印象的でした。年齢層についてはどうお考えですか?
年齢にはこだわっていません。重要なのはカルチャーフィットです。
上の世代で経験豊富な方も大歓迎ですし、そういう方と若いメンバーが混ざることで、より強い組織になると思っています。
今後の目標・採用
── 今後の目標を教えてください。
生成AIの時代を代表する会社になることが、今の大きな目標です。
たとえば、インターネット時代を象徴する存在としてソフトバンクのような企業がありますが、私はnocallにもそうなれるポテンシャルがあると思っています。すでに良いスタートが切れているので、それを確かな形にして社会に根付かせていく。それが今、一番大切にしていることです。
── どのような人と一緒に働きたいですか?
やっぱり私は、目標はでっかいほうがいいと思っていて。
その大きな目標に対して、一緒にワクワクしながら、プレッシャーすら楽しめる人と働きたいです。いわゆるグロースマインドセットを持っていて、成長意欲が高く、前向きに挑戦していける人ですね。
私はよく「いいやつがいい」って言ってるんですが(笑)、お互いに信頼しあえて、高め合っていける仲間と一緒に歩んでいきたいと思っています。
── ちなみに、現在の働き方やオフィス環境についても教えてください。
基本的には対面勤務が前提です。今の拠点は、正直言ってかなりボロボロのアパートみたいな場所なんですけど(笑)
でも、私はあえてこうした「ボロボロの場所」から始めることこそ、スタートアップらしいと思っているんです。後になって「あの小さな場所から始まったんだよね」と振り返ることができる、“物語のある原点”を持つことは、すごく意味があると感じています。
2025年5月から五反田のオフィスへ移転予定ですが、根底にある想いとしては、「赤羽のこの空間でも一緒にやれる人」と働きたいという気持ちが強いです。
スタートアップの本質に共感し、環境よりも志で動ける人と一緒に、これからの事業をつくっていきたいですね。