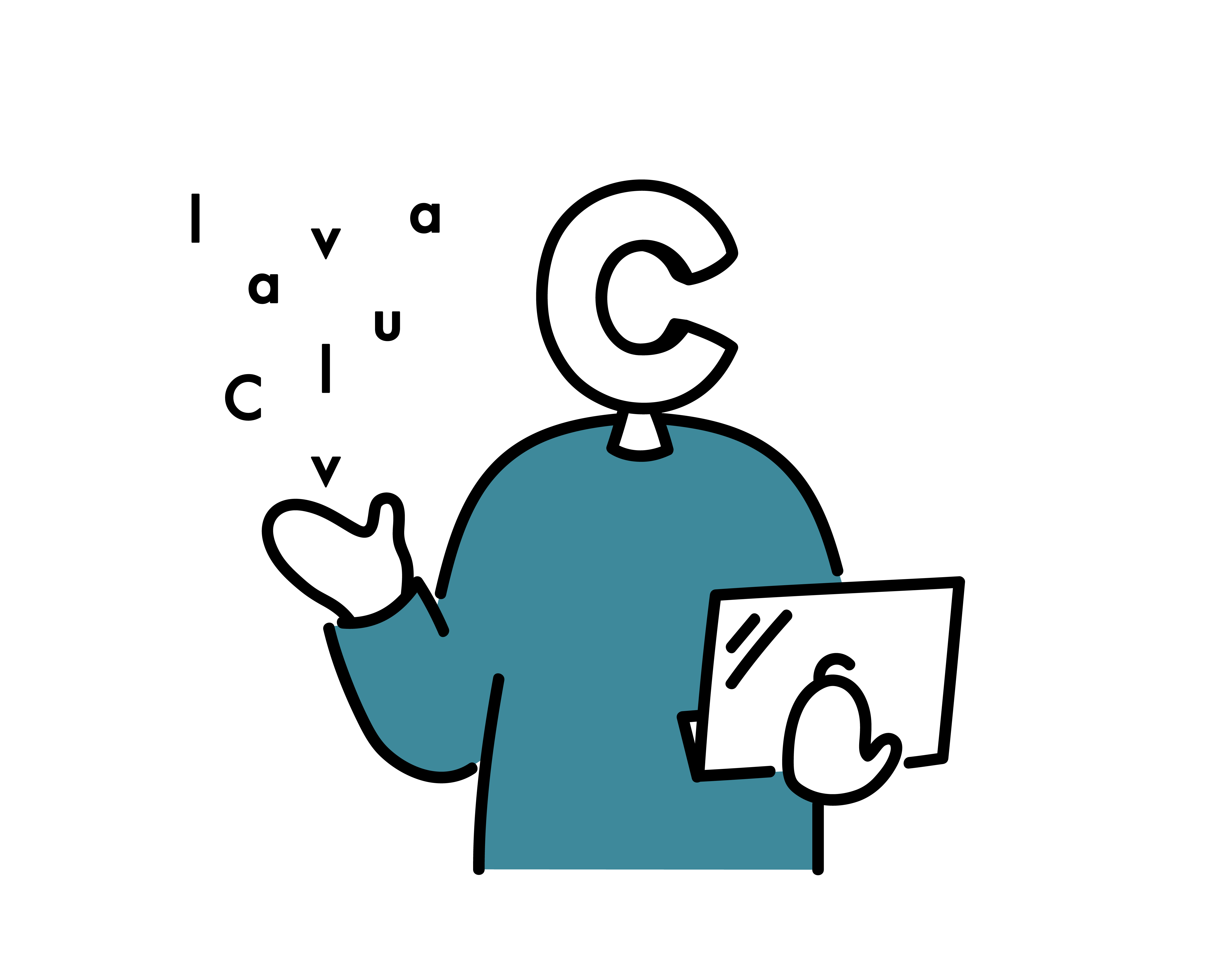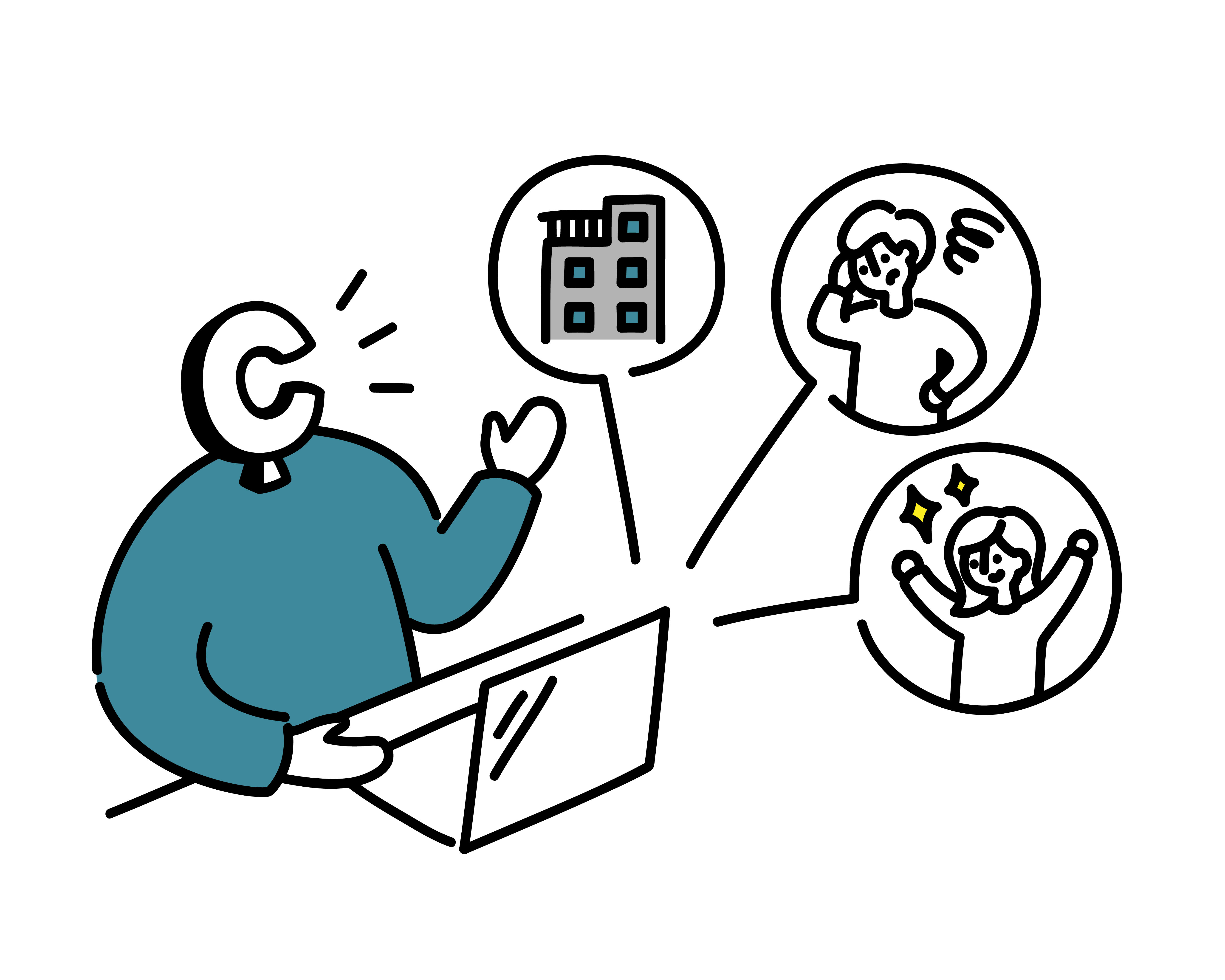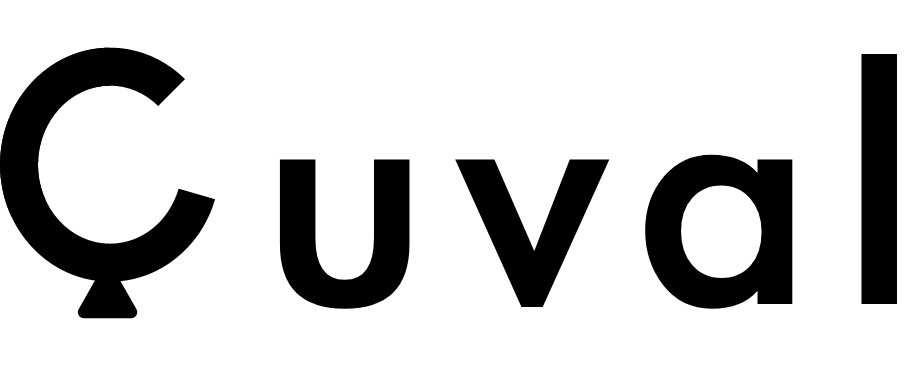森田 悟史氏|Securitize Japan株式会社 テックコンサルタント
東京工業大学大学院で情報科学を専攻。NTTデータにて銀行APIなど金融ITを9年間担当後、2018年に株式会社BUIDLの創業メンバーとして参画。2019年の米Securitizeによる買収を経て現職。現在は日本におけるデジタル証券/RWAの実装を牽引し、発行から流通、制度対応までを幅広く支える。
Securitize Japan株式会社

事業内容と市場背景
── 御社の事業内容からお聞かせいただけますか。
最近「RWA(Real World Asset:現実世界資産)」という言葉を耳にする機会が増えています。ブロックチェーンは、ネットワーク上で価値を電子的に表現したり移転したり、所有権を明確に示したりすることを得意としています。私たちが取り組んでいるのは、その中でも「有価証券のトークン化」です。証券(セキュリティ)をデジタル上で表現することから、「セキュリティトークン」「デジタル証券」と呼ばれてきましたが、近年はRWAという概念の一部として語られることが増えています。
Securitizeは2017年に米国で創業し、現在はRWAのトークン化領域で世界最大のシェアを持つ企業となっています。日本では2019年末から事業を開始し、2020年に国内で有価証券のトークン化を認める法整備が整ったことを契機に、本格的に事業を展開してきました。米国ではライセンスを取得し、証券業や原簿管理、セカンダリーマーケットの運営まで行っていますが、日本法人ではライセンスを保有しておらず、発行体や資金調達を行う企業にトークン化するためのプラットフォームを提供する立場を取っています。
── 2024年3月に大きな動きがあったそうですね。
世界最大の資産運用会社であるブラックロックが、弊社プラットフォームを活用して、MMF(マネー・マーケット・ファンド)を裏付け資産とするトークン『BUIDL(ビドル)』をローンチしました。これを起点に市場は一段と拡大し、世界的な注目が一気に高まりました。
── 競合との違いについてはどうお考えですか。
日本では証券会社を通じてデジタル証券を販売するケースが多く、投資家にとっては「トークン化されている」という実感を得にくい状況です。弊社は証券会社を介さず、発行体から投資家へ直接販売できる自己募集を可能とする「End to End」のプラットフォームも提供している点が大きな特徴です。
また、日本のデジタル証券はプライベートチェーン主体で進んでいますが、グローバルではパブリックチェーンが主流です。弊社は現時点で15種類の主要パブリックチェーンをサポートしており、案件ごとに最適なネットワークを選択できます。また、最近の事例ではマルチチェーン対応での流通が進んでおり、その点は世界的にも優位性のあるモデルといえます。実際、ブラックロックのBUIDLは現状7つのブロックチェーンで同時に流通しています。
── グローバルと日本市場の違いについても教えてください。
伝統的な金融商品とデジタル証券について、日本では不動産や映画、ポイント投資など新しい商品設計による差別化が模索されています。プライベートチェーン主流の日本では、そのように商品自体に目新しい要素がないと、既存の金融商品との対比で差別化をすることが難しい点が背景にあると感じています。一方、米国では伝統的金融商品をそのままパブリックチェーン上に流通させる動きが加速しています。背景にはオンチェーン上で生活や事業を営むプレイヤーが存在し、彼らが伝統的金融商品を求める需要があるからです。昨年のブラックロックの参入以降、この流れは一気に加速しました。また、その流れは今年さらに加速し、株式など様々な商品がオンチェーンに拡大しています。オンチェーン上で伝統的金融商品を保有することが当たり前になる日が近づいていることを感じます。
今後、日本でもステーブルコインの普及によりオンチェーン経済が可視化されれば、米国同様の動きが広がると見ています。その際、すでにグローバルで多数の実績を持つ弊社の優位性が、さらに鮮明になると考えています。
森田さんのキャリア

幼少期から大学時代
── どういう幼少期を過ごされたのでしょうか。
そうですね、あまり聞かれることはないですが、一言でいうと「新しいもの好き」でした。ハイパーヨーヨーやたまごっちといったブームになりそうなものを、流行する前から触ってみるのが楽しくて、発売されたらすぐに購入して遊んでいました。
高校は地元の公立校に進学し、そのまま東京工業大学へ進学しました。理系科目、とくに物理が面白いと感じていたので、なんとなく理学系に進みました。当初は物理志望でしたが、大学の授業で触れた情報系が思いのほか面白く、次第にのめり込むようになりました。ITリテラシーやプログラミングの授業が特に印象的で、2年次からは情報科学系に進むことを決めました。
その後はプログラミング言語の研究室に所属し、大学院まで進学。分散動的アスペクト指向言語の研究開発を行いました。今思えば、「分散」というテーマが、現在取り組んでいるブロックチェーンの世界につながっていると感じます。
NTTデータでの経験
── 新卒ではNTTデータを選ばれたのですね。
はい。先輩方の雰囲気が良かったのと、大規模システムに携わりたいという思いからNTTデータに入社しました。9年間在籍し、主に銀行系のシステムに携わりました。具体的にはインターネットバンキングや銀行API(パブリックAPI)の開発です。ちょうど銀行がAPIを公開し始めた時期で、まさにそのプロジェクトの中心に関わることができました。
銀行システムは非常に厳格な手続きや高いセキュリティ基準が求められるため、その環境で揉まれた経験は、現在の金融機関向けの事業に大いに活きています。
ブロックチェーンとの出会い
── ブロックチェーンに関心を持ち始めたきっかけは何でしょうか。
2017年末から2018年にかけての仮想通貨バブル期でした。当時のイーサリアムの「スマートコントラクト」に触れ、プログラミングが可能なブロックチェーンプラットフォームの可能性に惹かれました。一方で、当時のUXは非常に悪く、 CryptoKittiesといったサービスを使っても「ブラウザ拡張でしか動かない」「スマホで触れない」といったウォレットの不便さが目立ちました。
「これでは普及しない、スマホで触れなければ意味がない」と感じ、個人でブログを書きながらスマホで使用出来るウォレットについて調べて発信していたところ、Trust WalletのCEOから直接メッセージをもらい、日本でのコミュニティ運営や翻訳を手伝うことになりました。2018年はNTTデータに在籍しながら、毎日のようにミートアップや勉強会に参加し、ネットワークを広げていった時期です。
Securitize参画
── そこからどのように現在につながったのでしょうか。
2018年末、ミートアップで繋がったきっかけから、ブロックチェーン領域での知見を活かそうと、株式会社BUIDLに初期メンバーとして参画しました。大手企業を相手に、ブロックチェーンのコンサルティングや受託開発を行う会社です。金融系システムの経験を持つ自分にとって非常に合致する領域で、「ここに本気で飛び込みたい」と感じ、NTTデータを退職して参画しました。
その後、BUIDLは事業を拡大し、1年後には米Securitizeに買収されることとなります。これが現在のSecuritize Japanにつながる大きな転機でした。

BUIDL立ち上げ〜Securitize参画
── 前身の株式会社BUIDLには創業メンバーとして参画されていますが、最初に取り組んだことは。
立ち上げ当初はほぼ“ゼロからの営業”でした。VCのグローバル・ブレイン経由のご紹介や周辺のネットワークはあったものの、基本は自分の足で各社に出向き、「ブロックチェーンで何ができるのか」を説明して回る日々。ちょうど新規事業系の部署でPoC(概念実証)ニーズが高まり、各社のコンペに次々と応募・提案しました。
NTTデータ時代に鍛えられた提案書づくりや“相手の立場で価値を言語化する力”が活き、受注は順調。結果として1年で10件前後のプロジェクトを同時並行で回すことになりました。案件ごとに、プロジェクトマネージャー1名に対し、エンジニアやリサーチャー、業務委託を組み合わせる少数精鋭体制。睡眠時間や週末を削るほどのハードワークでしたが、やり切った経験は大きな自信へとつながりました。 テーマはセキュリティトークンや再生可能エネルギーなど多岐にわたり、PoCが乱立した時期でもあったため、ブロックチェーンの本質的価値を掘り下げ続けた1年でもありました。
── その後、2019年12月にSecuritizeへ。
グローバル・ブレインはSecuritizeの株主でもあり、当社の日本進出に際して「現場力のある良いチームがいる」と声がかかったのがきっかけのようです。結果としてBUIDLは買収され、日本法人の核になりました。現場にいた私を含め、多くのメンバーにとっては青天の霹靂でしたね。
買収直後の変化と学び
── 買収後、現場はどう変わりましたか。
すぐに旧案件を「明日からゼロ」にはできません。進行中の案件をクローズへ導きつつ、SaaSベンダーとして自社プロダクトを深く理解し、日本で機能させるためのローカライズ要件を洗い出す――作業量は一気に増えました。
ちょうど2020年5月、日本でデジタル証券(セキュリティトークン)関連の法整備が進んだタイミングでもあり、勉強会や実務者コミュニティにも参加。私は当時から「最終的にはパブリック・ブロックチェーンが主流になるべき」と主張していましたが、暗号資産の流出事件後の空気感もあり、国内は“まずは極力リスクを取らない”設計が主流。投資家保護の観点では堅牢である一方、テクノロジーの良さをどう両立させるか――このギャップの埋め方を、日本の枠組みの中で戦略的に設計していくのは課題でした。
この仕事の面白さ/事業の魅力
── やりがいを感じる点は。
この領域を“最初期”から追ってきたからこそ、日本の進化に手応えを与えられるポジションにいられること。そして、自分の確信――「パブリックが主流になる」という見立てが米国の動きと一致し、実際に結果が出て説得力が増していることです。
もう一つは、当社がB2Bの裏方にとどまらず、エンドユーザーが実際に触れる画面を提供している点。丸井グループ、ソニー銀行、クレディセゾン、PPIHなど大手企業の先で、多くのユーザーが当社プラットフォームを通じて投資体験をしています。ローンチの瞬間に、自分自身もユーザーとして触れられる――責任は重いですが、事業者冥利に尽きます。
現在の業務範囲
── 現在の業務内容を教えてください。
コーディング以外は一通り担当します。新規提案、顧客折衝、プロジェクトマネジメント、ローンチまでの並走が中心です。採用は固定担当を置かず、案件やフェーズに応じて最適なメンバーが面接・評価に入るスタイル。必要に応じて前に出る“全員リクルーティング”に近い運用です。
組織体制と取り組み
── 現在の組織体制や人数について教えてください。
現在、日本法人は10数名ほどで、グローバル全体では200名規模です。「そんなに少ないのですか」と驚かれることも多いですが、全員がフルリモートで、自立して動けるメンバーが揃っています。ビジネスとエンジニアがちょうど半々の構成です。
── 実際の案件では、どのようにプロジェクトを回されているのでしょうか。役割分担やチームの動き方について教えてください。
営業も兼ねる3名ほどがプロジェクト管理や要件定義・テストを担い、私もそこに含まれています。設計やコーディングを行うのは、リードエンジニアを筆頭とするフルスタックエンジニア達です。基本的には3名のプロジェクトリーダーがそれぞれで案件を回す形です。もちろんお互いで、フォロー役に回ることもありますね。
── 組織として特に注力している取り組みは。
もちろん最も重要なのは、Securitizeのソリューションを利用する顧客を増やすことです。そのうえで、日本においてパブリック・ブロックチェーンを活用したセキュリティトークンを広める活動に特に力を入れています。米国で既に実現している事例を紹介し、「ここまで来ている」という未来像を示すことが、日本市場を前進させるうえで大切だと考えています。
── NTTデータ時代には個人でブログもされていたそうですが、今も同じように続けられていますか。
いえ、今はやっていません。現在は会社の立場として発信しています。たとえば昨年3月にブラックロック社がローンチした「BUIDL」という商品は、非常に画期的な取り組みでした。最大手でありながらフルにパブリック・ブロックチェーンにベットするアプローチで、それまでの伝統的金融の常識からは大きく異なっていたんです。
従来は投資家保護の観点から「購入した証券は預かってあげます」というモデルが一般的でしたが、BUIDLは基本的に投資家自身のウォレットに直接発行する仕組み。預からずに自分のウォレットで保有・活用できるのは、日本の大手金融機関ではなかなか想像できない形でした。
こうしたインパクトの大きい事例は、日本の金融機関にもきちんと伝える必要があると考えています。ですので現在は、企業の立場で各社を訪問し、「いまグローバルで何が起きているのか」を啓蒙する活動をプロジェクトを回すことと並行で続けています。
── 組織としての強みや課題について教えていただけますか。
そうですね。良い点はやはり フルリモートで、それぞれが自由かつ責任を持ってオーナーシップを発揮しているところです。中途半端な姿勢で取り組むメンバーはいません。全員が自立したプロフェッショナルとして効率的に動けているのは、少数精鋭の組織ならではの良さだと感じます。
一方で課題は、まだ事業として一気にスケールする段階に至っていない点です。セキュリティトークンのプラットフォーム事業は、1件あたりが長期スパンのプロジェクトになることが多く、どうしても「重い」案件が中心です。SaaSのように月額課金ユーザーが一気に増えてARRやMRRが急成長する、といった世界にはまだ到達していません。次のフェーズでは、そうした規模感にどうアプローチしていくかが大事になると思います。
今後の目標
── ありがとうございます。では、その先を見据えた今後の目標を伺えますか。
短期的には、やはり パブリックブロックチェーンでの取り組みを日本に広げていくことです。中長期的には、資本市場そのものを変えていきたい。資金を調達したい人と投資したい人が効率的につながり、規制を守りながらも円滑な資金循環を実現する。それによって日本経済全体を活性化することが、私たちの大きな目標です。
── その未来を共に目指す仲間として、どのような人と働きたいですか。
ブロックチェーンや資金調達の可能性を「信じて突き進める人」ですね。未来到来を半信半疑で眺めるのではなく、実装に責任を持ってコミットできる人。カルチャー面ではフルリモートの環境下でも、月1回のカジュアルな集まりで自然に交流を楽しめる人が合うと思います。
日本でも資本市場のデジタル化を本格的に進め、資金がより自由に循環する経済をつくる。 規制順守と技術の利点を両立させながら、その実装を現場で積み重ねていく――それが、私たちがこれからも担っていく役割です。