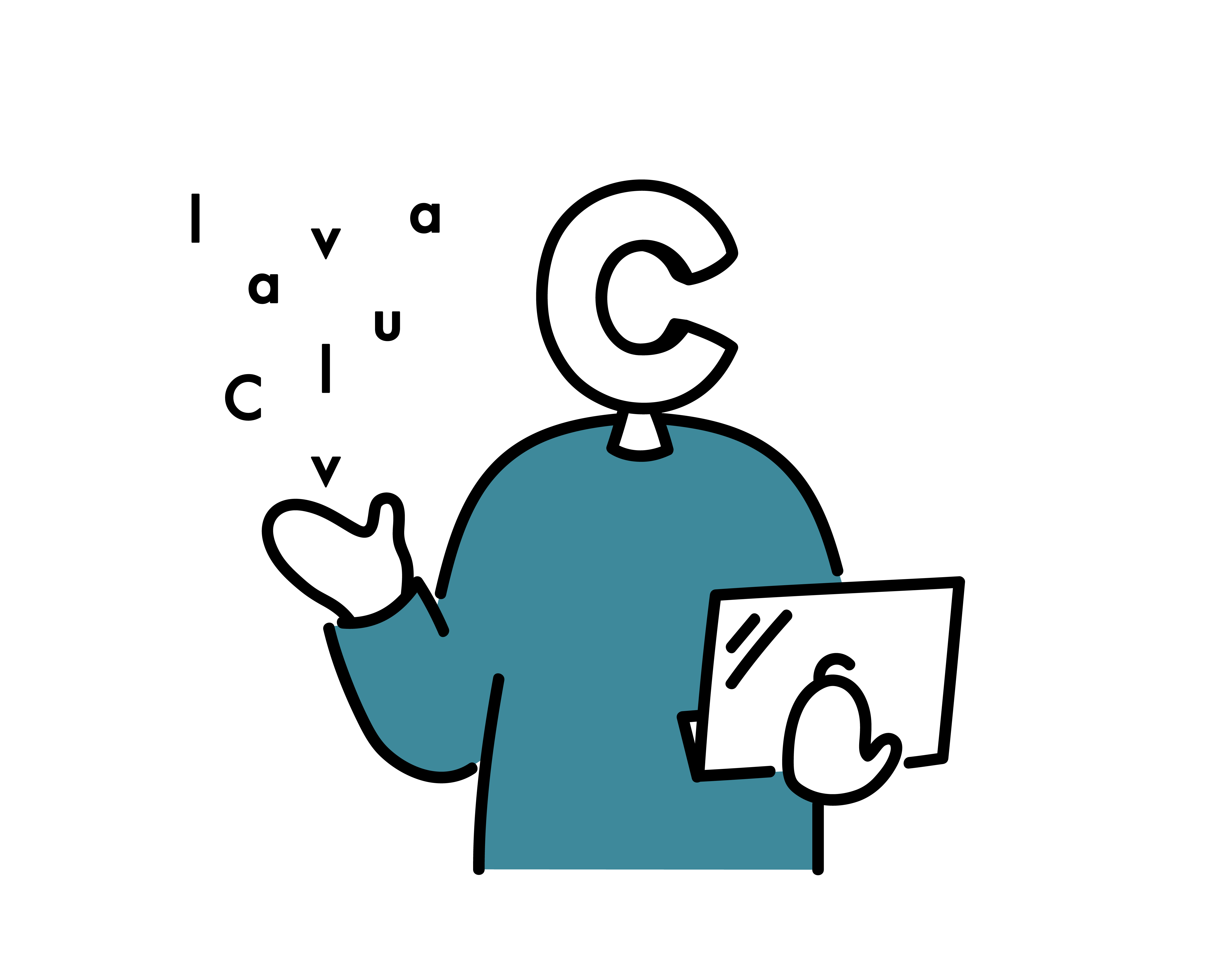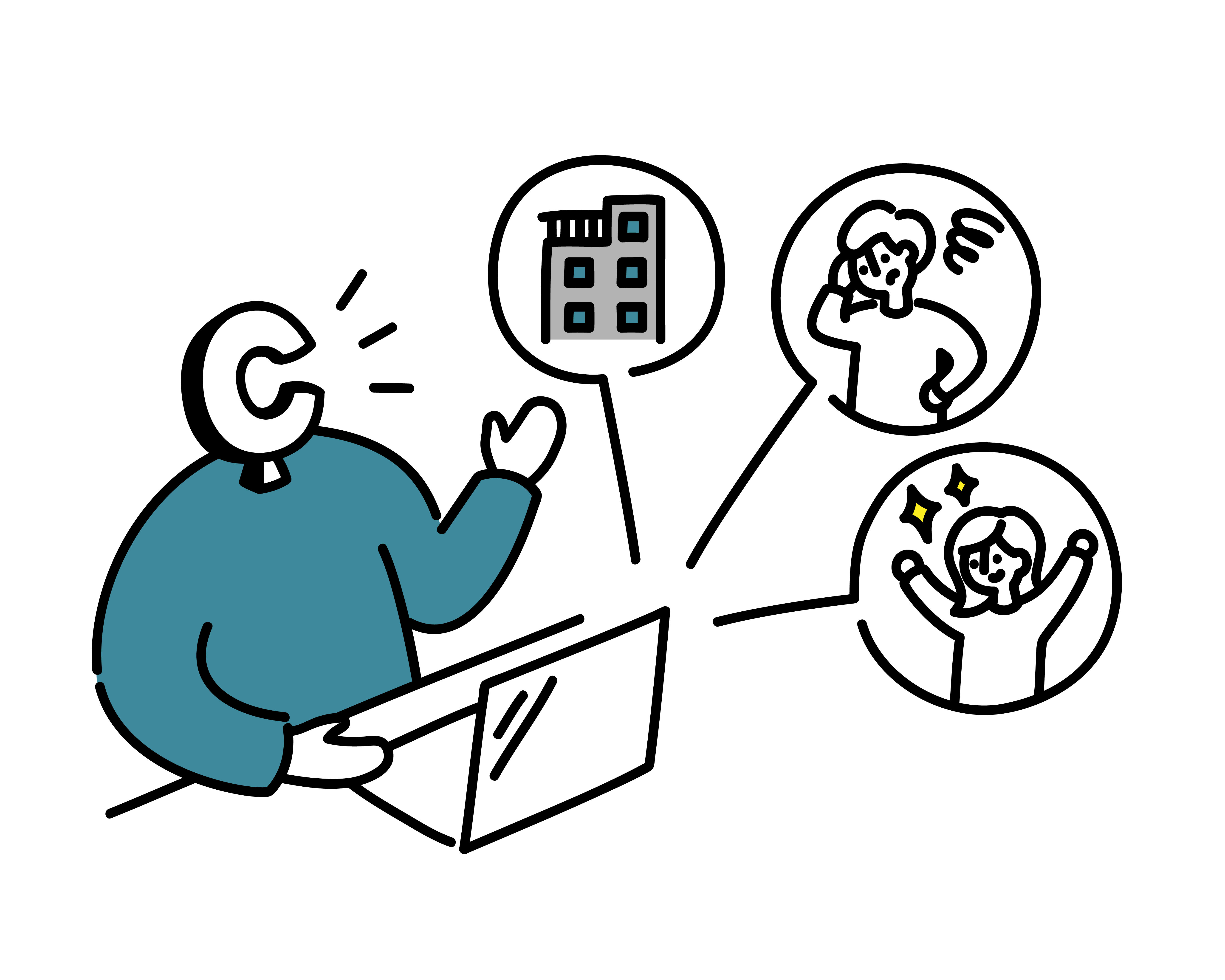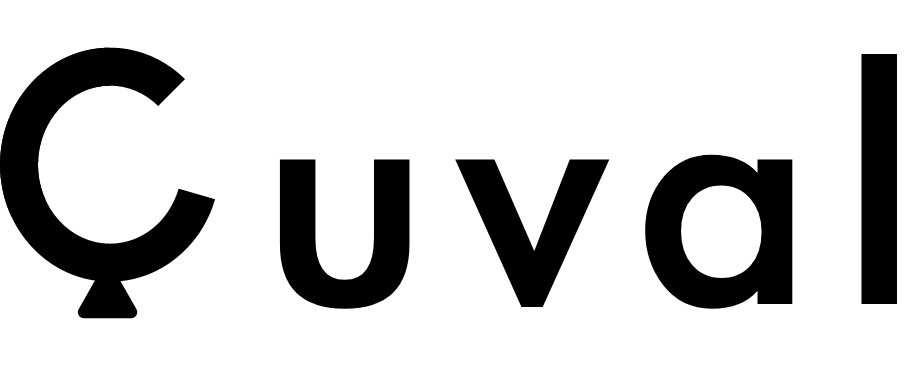加藤 彰宏 氏|株式会社Schoo 執行役員CTO
早稲田大学卒業後、SIerやWeb系企業、楽天などを経て、スターフェスティバルにてCTO兼事業長を務めた後、独立。技術顧問として40社以上のプロダクト開発支援に関わる。2024年よりSchooのCTOに就任。「学習を通じて社会に価値を届ける」ことをテーマに、プロダクトと組織の成長をリードしている。
株式会社Schooについて
── 御社の事業内容を教えて下さい。
Schoo(以下スクー)は「世の中から卒業をなくす」というミッションのもと、社会人向けのオンライン学習サービスを展開しています。私たちは誰もが制約にとらわれず「学び続けられる社会の実現」を目指し、主に社会人向けの複数のサービスを提供しています。
まず一つ目が、法人向けの「Schoo for Business」です。これは、企業の社員研修や自己啓発を支援するオンライン学習サービスで、組織の学びを継続的に促進する仕組みを提供しています。
二つ目は、個人向けの「Schoo for Personal」です。こちらは生放送形式で学べる学習コミュニティに近く、ビジネススキルからライフスタイルまで幅広いジャンルのコンテンツを提供しています。生放送は無料で視聴でき、過去の授業は録画でいつでも振り返ることが可能です。
三つ目に、高等教育機関向けの「Schoo Swing」があります。大学や専門学校といった教育機関のDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するプラットフォームで、高等教育現場のオンライン化を後押ししています。
さらに、地域創生を目的とした取り組みにも注力しています。遠隔教育による人材育成を起点に、全国の自治体と連携し、地域活性化に寄与するサービスを展開中です。都市部だけでなく、どこにいても学びにアクセスできる仕組みを築くことで、「学びの格差のない社会」の実現を目指しています。
加藤さんのキャリア
── 幼少期はどのように過ごされていましたか?原体験につながるようなお話があれば、ぜひ教えてください。
幼少期は、親の仕事の都合でブラジルに住んでいました。3歳から6歳までですね。当時は日本語とポルトガル語を明確に区別することなく生活していたため、言語に対する感覚がやや曖昧だったように思います。
その影響もあってか、日本に戻ってからは人と話すことに少し抵抗があり、どちらかというと寡黙な子どもでした。高校を卒業するまでも、あまり自分から積極的に人と話すタイプではなく、常に頭の中で考え事をしているような性格でしたね。
── “考える時間”を大切にされていたんですね。
はい。高校までは片道30分ほどかけて徒歩通学していたのですが、その1時間の往復が、今思えば“思考の時間”になっていたんです。特に何かテーマを決めていたわけではありませんが、日々さまざまなことを頭の中で巡らせていました。その習慣は、今の自分の思考スタイルのベースになっていると感じています。
── 加藤さんはさまざまなスポーツに取り組まれてきたと伺いましたが、最初に始めたスポーツは何だったのでしょうか?
最初に取り組んだのは水泳です。ブラジルに住んでいた幼少期に始めて、日本に帰国してからも中学まで続けていました。また、小学生の頃にはラグビーも始めて、小学校、中学校と継続していました。その後はバドミントンを経て、大学ではテニスに。社会人になってからはゴルフやトライアスロンにも挑戦しています。
── ではここから、大学時代について伺っていきたいと思います。加藤さんは早稲田大学に進学されていますが、選んだ経緯があれば教えてください。
正直に言うと、強い志望動機があって選んだわけではなくて、「なんとなく」入学したというのが本音です。ただ、実際に入ってみると、早稲田には“泥臭くやり切る”文化があって、それが自分にはとても合っていたなと感じました。
── 大学ではどのようなことを学ばれていたのでしょうか?
専攻は数学で、特に幾何学模様がどのようなパターンで成り立っているかを研究していました。論理的な構造を読み解いていく内容が多く、今の思考スタイルにも通じるものがあったと思います。
── 大学時代のアルバイト経験についてもお聞きしたいのですが、加藤さんのnoteでマクドナルドでの経験が紹介されていて、とても印象的でした。
あれは、自分の人生にとって大きな転機でした。お金を稼ぐというより、社会を経験する目的で始めたのですが、最初は人と話すのが苦手だったので厨房担当からスタートしました。
ところが、入って間もなく「マネージャーをやってみないか」と声をかけられたんです。当時は時給もかなり低かったので、「マネージャーになれば時給が上がるんですか?」と聞いたら「上がります」と言われて(笑)。軽い気持ちで引き受けたのが始まりでした。
── 実際にやってみて、いかがでしたか?
想像以上に責任のある仕事でした。接客、注文管理、資材管理、アルバイトの育成やシフト調整まで、店舗運営のすべてに関わるポジションだったんです。
中でも大きかったのが「接客」の経験です。人と話すのが苦手だった自分が、さまざまなお客様と接する中で、「対話って面白いんだ」と気づくことができました。知らない人と話すことの楽しさを初めて実感した体験でした。
── まさに、コミュニケーションに対する意識が変わったんですね。
そうですね。そしてもう一つ大きかったのは、「店舗運営」という視点を持てたことです。アルバイトながら、現場の全体を見渡して動かす経験をしたことで、「これはある意味、小さな会社経営だ」と感じるようになりました。この経験が、自分のキャリアの原点になっていると思います。
── マクドナルドでのマネージャー経験が、今の加藤さんの原点というわけですね。
まさにそうです。もしあの経験がなかったら、今とは違う人生を歩んでいたかもしれません。もっと寡黙なまま、エンジニアリングに没頭する道を進んでいた可能性もあると思います。
── では、ここからは大学卒業後のキャリアについて伺っていきます。最初はSIerに入社されたとのことですが、なぜその道を選ばれたのでしょうか?
大学進学のときと同じで、就職に対しても強い意志があったわけではありませんでした。同じ学部の周囲の友人たちがSIerを目指しているのを見て、「みんなこの業界に行くんだな」と思い、なんとなく興味を持ったというのがきっかけです。
とはいえ、まったく無関心だったわけではなくて。いとこが一つ上の代でパソコンに詳しく、自分も祖父に買ってもらったパソコンをきっかけに自然とプログラミングに触れていました。その頃の自分の感覚としては「みんなパソコンくらいやってるでしょ」と思っていたんですが、後になってそれがかなり特殊な環境だったことに気づきました(笑)。
── 実際に入社されてからは、どのような仕事を担当されていたのでしょうか?
主に、工場関連の業務システムの構築を担当していました。約4年間在籍し、その間に工場に付随する複数のシステムにも関わりました。最終的には、別プロジェクトを単独で任されるなど、エンジニアとしての基礎をしっかりと築けた時期だったと思います。
── そこからWeb業界に転身された理由は何だったのでしょうか?
2004年ごろ、ちょうど世の中が急速にブロードバンド化して、インターネットが大きく広がっていった時期でした。それまで自分が開発していたのは、主に工場などのクローズドな環境で使われるクライアントアプリケーションでしたが、「もっと多くのユーザーに、直接届くものを作りたい」という思いが強くなったんです。
いまで言う“リスキリング”が必要な領域への転身でしたが、それでも「ユーザーの顔が見える場所で、自分の技術を活かしたい」という気持ちが勝って、Web業界へ進む決断をしました。
── この頃から、noteにも書かれていた「スペシャリスト思考」ではなく「プロフェッショナル思考」に変わっていったのでしょうか?
まさにそうです。その原点についても、マクドナルドでのアルバイト経験にあると思っています。マクドナルドはアメリカ発の企業ということもあり、業務マニュアルが非常に体系的に整備されていて、従業員が常に「どうすれば顧客満足度を高められるか」を意識しながら働く文化が根づいていました。
その考え方は、社会人になってからも自分の働き方に大きく影響を与えています。単に技術を磨くことに終始するのではなく、「そのサービスを使う人がどう感じるのか」を常に意識しながら設計・開発に取り組むようになりました。
だからこそ、いわゆる“職人的なスペシャリスト”ではなく、“ユーザーに価値を届けるプロフェッショナル”でありたいという意識が、自然と自分の中に根づいていったのだと思います。
── ではここからは、楽天とスターフェスティバルでのご経験について伺いたいと思います。それぞれ、どのような背景があったのでしょうか?
まず楽天についてですが、前職のWeb系企業では、さまざまなアプリケーションの開発に携わり、自分が中心となってプロダクトをつくることも多くありました。ただ、あるときクライアントから「もっと大規模なシステムをつくってほしい」という依頼があり、自分の経験やスキルでは対応できる範囲に限界があることを痛感しました。
1000万人、1億人といった規模のユーザーを対象にした開発経験はなく、そのノウハウを得るには「実際にその環境に飛び込むしかない」と思ったんです。
英語は苦手だったこともあり、海外企業は選択肢に入らず、国内で1億人規模のユーザーを抱える企業を探した結果、「楽天、それも楽天市場しかない」と確信しました。そこからは楽天市場一本に絞って転職活動を行いました。
── 実際に楽天では、どのような形で入社されたのでしょうか?
楽天には、キャリアを問わず全員が平のエンジニアからスタートするというルールがありました。私も例外ではなく、新卒の方が上司というチームに配属されました。そこから現場で経験を積み、最終的にはグループマネージャーを任されるようになりました。
── そこからスターフェスティバルに移られた背景には、どのようなきっかけがあったのでしょうか?
2010年、楽天の社内公用語が英語になったタイミングで、苦手な英語に向き合いながら必死に食らいついていました。ただ、その頃には「技術を習得する」というフェーズは終えていて、むしろ「楽天市場をどう成長させるか」を考えるようになっていたんです。
とはいえ、英語をより上達させる機会や海外赴任のチャンスはなかなか巡ってこず、そんな中、テニス仲間から「ビズリーチに登録してみたら?」とすすめられ、軽い気持ちで登録したことが転機になりました。そこで、国内のスタートアップが非常に面白いことをしていると知り、「英語にこだわって楽天にとどまるか、自分の経験をスタートアップで活かすか」という選択肢が浮かび、最終的には後者を選びました。
── スターフェスティバルを選ばれた決め手は何だったのでしょうか?
当時は複数の会社から内定をいただいていましたが、今思えば、スターフェスティバル以外はほとんどが後に上場を果たすような企業でした。その中で、スターフェスティバルが最も条件的に厳しく、「一番やりがいを感じられそうだ」と思えたんです。だからこそ、あえて一番チャレンジングな環境を選びました。
── 実際に入社されてからは、どのような役割を担われていたのでしょうか?
入社して数ヶ月後には取締役CTOに就任し、フードデリバリーサービス「ごちクル」の開発を中心に担当しました。後半は事業責任者も兼任し、最終的にはプロダクトと事業の両方をリードする立場に。約5年間在籍し、スタートアップならではのスピードと密度の中で、非常に多くのことを経験させてもらいました。
── ここからは、独立のタイミングについて伺っていきたいと思います。株式会社Plus10Percent を立ち上げていらっしゃいますが、その経緯について教えていただけますか?
はい。理由は大きく2つあります。
一つ目は、スターフェスティバルで取締役として仲間を採用し、事業を支えてきた中で、「この会社には今後も成長していってほしい」という強い思いがあったことです。ただ、自分自身としては「他社に転職する」という選択肢よりも、「自分のやりたいことを追求しながらも、支援は継続する」ような関わり方を望んでいました。その結果、独立という形を選びました。
もう一つは、CTOとしての経験を重ねる中で、自分が得意とする領域や最大限に価値を発揮できるスタイルが明確になってきたことです。その力を一社だけに集中させるのではなく、複数の企業に対して提供することで、より大きく社会に貢献できると考えたことが、Plus10Percent を立ち上げたきっかけになっています。
── 実際、これまでに40社近くをご支援されているというのは本当にすごいですね。その中には、キュービックさんや助太刀さんも含まれていると伺いました。
はい。どちらも現在も継続して関わっている企業です。
── それぞれ、どのような経緯で関わりが始まったのでしょうか?
キュービックについては、同社のオフィスに間借りしていた起業家の方がいて、「加藤さんと相性が良いと思う」とご紹介いただいたのがきっかけです。助太刀の方は、当時ユーザベースのCTOだった竹内さんから「ぜひ力を貸してあげてほしい」とお声がけいただき、それが関わりのスタートで、創業初期から伴走させていただいており、今も継続して支援を続けています。
── これまでのご経歴の中で、特に印象に残っている出来事や、転機になった経験はありますか?
楽天時代に担当した「楽天市場の購入履歴」の開発業務は、今振り返っても非常に印象に残っています。全ユーザーの購買データを扱う重要な機能で、創業当初から蓄積されてきた大量のデータベースが限界に達しており、パフォーマンス改善が大きな課題でした。
その当時、パフォーマンスに関する課題が表面化し、改善が急務となる中で、私はシステム全体の再構成に着手しました。ちょうど三連休を使ってサーバーの構成を見直し、ボトルネックの解消や処理速度の向上に取り組みました。結果的に、週明けには対応を完了させ、サービス品質の改善につなげることができました。
この経験を通じて、自ら主体的に課題を見つけて解決し、現場で成果を出すというエンジニアリングの本質に強く触れたと感じています。単に技術を磨くだけでなく、ユーザーにとって本当に価値ある体験を届けるという視点を持てたのは、この時の経験が大きかったと思います。
スクーとの出会い
── ここからは、現職であるスクーでの取り組みについて伺っていきます。きっかけは、スターフェスティバルのときと同様に、テニスを通じてのご縁だったと伺いました。
はい、そうです。取締役COOの古瀬とはテニスを通じて知り合いました。もともとキュービックさんや助太刀さんと同様に、技術顧問としての支援をご依頼いただいたのが最初の関わりです。
── そこからすぐに参画されたわけではなかったのですね。
はい。一度お話をいただいた後、しばらくやり取りが途絶えた時期もありました。その後、何度か対話を重ねる中で、「まずは顧問という形で関わるのはどうか」とご提案をいただき、2023年の秋ごろに再び接点が復活しました。
── 最終的に技術顧問としての参画を決めた決定打は何だったのでしょうか?
古瀬の本気度が強く伝わってきたこと、そして自分としても「これは解決できる領域だ」と感じたことが大きかったです。自身が運営する会社Plus10Percentとして支援をお引き受けする際は、常に「相手の本気度」と「自分が成果を出せるか」を大切にしています。
スクーからは当初から多くのインプットをいただいており、それらを通じて「この課題は自分が貢献できる」と確信を持てたため、「まずは技術顧問として入りましょう」と、2024年1月から正式に関わり始めました。
── 2024年1月にスクーへ技術顧問として参画された際、まずどのような業務から着手されたのでしょうか?当時、スクーから期待されていたミッションなどもあれば教えてください。
参画当初は、すでに別の技術顧問の方がいらっしゃったので、“ダブル技術顧問”のような体制でスタートしました。まずはその方と領域を明確に分けるところから始め、私はプロダクト開発を、もう一方は情報システム部門を担当するという形に整理しました。
そのうえで、プロダクト開発における課題抽出のために、社内の関係者へヒアリングを実施しました。最初から網羅的にというよりは、事前にいただいていた情報をもとに「この辺りに課題があるのではないか」という仮説を立て、それを検証する形で進めていきました。結果として、仮説と実際の課題がほぼ一致しており、スムーズに本質的な論点にたどり着くことができました。
── そのような経緯を経て、2024年4月にCTOへ就任されたとのことですが、その意思決定にはどのような背景があったのでしょうか?
noteにも書いたとおり、やはり代表の森との出会いが大きかったですね。それに加えて、自分自身のキャリアに対する内省も大きく影響しています。
私はこれまで基本的に、自分の“経験”をもとに業務に取り組んできました。たとえば書籍を読んでも、「これは自分が現場で実践してきたことと同じだな」と感じながら読み進めるようなタイプで、20代から40代中盤くらいまでは、そうした“経験ベース”で判断し行動することがほとんどでした。
ところが独立後、複数の経営者や企業と関わる中で、「自分の語彙や知識には限界がある」と痛感する場面が増えてきたんです。経営的な視座での対話や意思決定が求められる場面も増え、より広く、より深く学び直す必要性を強く感じるようになりました。
そこで、研修や読書、事例研究などを通じて、経験と理論の両輪で自分をアップデートすることに注力しました。その結果、明らかにアウトプットの質が高まり、「学び続けること」そのものが、いかに重要かを再確認しました。
── “学び続けること”がテーマのスクーと、まさに重なる部分ですね。
そうなんです。ちょうどそんな実感を持っていた時期に森と出会い、スクーのミッションやビジョンを聞いて、強く共感しました。スクーは「社会人が学び続ける意味」を体現するサービスです。これまでの自分の経験と、学び直しを通じて得た知見──その両方を重ねられる場として、CTOとしてジョインする決断をしました。
── 現在もキュービックさんや助太刀さんの技術顧問を続けながら、スクーのCTOも務めていらっしゃいますが、これらをどのように並行して進めているのでしょうか?
よく聞かれるのですが、ポイントは「脳の使い分け」にあります。
私の中では“脳内にフォルダがある”ような感覚があって、会議中に話題が出ると「これはこのカテゴリのこのトピックだな」と分類して記憶しておくんです。次に同じ話題が出たときには、そのフォルダをパッと開いて、必要な情報をすぐに取り出すイメージです。
ですので、複数のプロジェクトを同時に進めること自体は、あまり苦ではありません。あとは時間の使い方さえしっかり管理すれば、無理なくやっていけるという感覚ですね。
スクー CTO正式ジョイン後
── 2024年4月にCTOに就任されてから、業務内容や心境に変化はありましたか?
一番大きな変化は、「使える時間が格段に増えた」ことですね。技術顧問として関わっていたときは、限られた時間の中で仮説ベースで課題を抽出していましたが、CTOになってからは、それを“網羅的にチェックするフェーズ”に移行しました。
つまり、仮説に頼るのではなく、プロダクトや組織のあらゆる項目を一つずつ丁寧に確認しながら、「課題があるのか、ないのか」を全体俯瞰で洗い出すというアプローチに切り替えたんです。結果として、外部の立場では見えなかったような本質的な課題にも、深く入り込んでアプローチできるようになりました。
── 実際にスクーの中に入ってみて、苦労した点や、逆によかったことはありますか?
苦労したことはたくさんあったと思いますが、私はあまり「辛かった」「大変だった」という感情を長く記憶しないタイプなんです(笑)。何をやったかという“事実”はきちんと記憶に残っているんですが、ネガティブな感情はなるべく上書きしていくようにしています。
その分、「よかったこと」はしっかり覚えていて、たくさん話せます。スクーで特に感じるのは、「温かくて、協力的な人が本当に多い」ということですね。
何かを提案したとき、すぐに「やりましょう」と前向きに動いてくれる。この推進力は、プロダクト開発を進めるうえで非常に大きな強みだと思っています。
もちろん、関係性が浅くても動いてくれる方々ばかりですが、日々のコミュニケーションを通じて相互理解が深まることで、背景への納得感も増し、結果的にアウトプットのスピードも質もぐっと高まる。やはり、外部顧問として関わっていた頃とは、組織の中にいる今とでは、連携の密度もスピード感もまったく違うと感じています。
── 現在のスクーでの加藤さんの業務について伺いたいと思います。日々どのような業務に時間を割いていらっしゃいますか?
入社当初は、開発組織の基盤づくりの一環として「採用」にかなりのリソースを割いていました。ですが、現在は一定の採用が進んだこともあり、注力領域を「中長期の戦略立案とその実行」にシフトしています。
具体的には、これまでに抽出してきた組織的・技術的な課題に対して、「どう解決するか」「どう変化させていくか」というフェーズに入り、現場や経営陣と連携しながら実行に移している段階です。
── 改めて、Schooという事業の魅力を、加藤さんご自身の視点でお聞かせください。
Schooの最大の魅力は、「学び」が時間や場所に縛られず、誰でも手軽に体験できるという点にあります。
私自身、これまでのキャリアで「経験」と「学び」を通じて多くのことを得てきましたし、それが仕事や人生に与える影響は計り知れないと実感しています。だからこそ、社会人が継続して学び続ける場として、Schooのようなサービスには大きな意義があると思っています。
特に、生放送の授業が無料で視聴できる仕組みは非常にユニークです。金銭的なハードルが低く、多くの人に「学びの体験」を届けられるのは、他にはない強みです。
また、生放送ならではの“インタラクティブな学習体験”があるのもポイントです。たとえば、授業中にチャットで質問すれば、講師がその場で拾って答えてくれることもあります。録画視聴とは違う、「その場のやり取り」を通じた理解の深まりがあるんですね。
さらに、取り扱っているコンテンツの幅も非常に広く、「こんなテーマあるかな?」と検索してみると、大抵のジャンルが網羅されています。自分が「学びたい」と思ったタイミングで、すぐに知識にアクセスできるのも大きな魅力だと思います。
── “ライブ感のある学び”というのは、確かに他ではなかなか味わえない体験ですね。
おっしゃる通りで、実際に生放送中には受講者同士がチャットでコミュニケーションを取っていることもよくあります。「一人で学んでいる」というより、「みんなで学んでいる」という感覚があるんです。これはまさに、ライブイベントに参加しているような熱量のある体験です。
こうした参加型の学習スタイルは、学びを「義務」ではなく「楽しいこと」として捉えられるようになる良いきっかけになると思っています。Schooならではの価値ですね。
現在の組織について
── ここからは、スクーの開発組織について伺います。御社全体では、業務委託や派遣の方を含めて約250名ほど在籍されている印象ですが、開発組織としてはどのくらいの規模なのでしょうか?
現在、開発組織は40名強の体制で運営しています。
── その40名強のチームは、どのような体制で構成されているのでしょうか?
組織としては「開発本部」があり、その中に大きく2つの部門が存在しています。開発と開発支援という形で分けていますが、人数の構成でいうと、プロダクト開発を担う部門の方がやや多く、組織の中核を担っています。
── 現在、開発組織として特に注力されている取り組みがあれば教えてください。
はい。今は大きなテーマとして2つのプロジェクトに注力しています。一つは「APIの開発」、もう一つは「リアーキテクト(システム再設計)」です。いずれも中長期で見たときに、Schooのプロダクトや事業成長の基盤となる非常に重要な取り組みだと位置づけており、リソースを集中させて進めています。
── Schooは、コンテンツ制作から配信までを自社で完結されているのが大きな特徴だと思います。その中で、開発チームと撮影や運営チームとの連携もあるのでしょうか?
もちろんあります。中長期でプロダクトビジョンを設計していく際には、「コンテンツをどう進化させるか」と「プロダクトとしてどう成長させるか」を切り離して考えることはできません。撮影チームや運営チームといった他部門とも積極的に意見交換を行い、互いにビジョンを共有しながら進めています。
“開発だけ”で完結しないのがスクーらしさでもあり、プロダクトの未来を、部門を越えて一緒に作っていく姿勢を大切にしています。
── スクーの開発組織について、良い点や、さらに良くしていくための改善ポイントがあれば教えてください。
良い点としてまず挙げたいのは、少しお話しましたが、とにかく「温かく、協力的な人が多い」という点です。何かを提案すると「いいですね、やりましょう」と即座に前向きなリアクションが返ってくる。これは開発の現場において非常に大きな推進力になっています。
もう一つの特徴としては、「学習意欲の高さ」があります。これはスクーならではの文化だと思っていて、メンバーの多くがインプットだけでなく、その学びをどうアウトプットするかまで意識して動いているんです。
たとえば、我々が提供している「Schoo Swing」を活用して、開発メンバー自身が“講師”として社内向けにナレッジを配信する取り組みが自然に生まれています。誰かが「このテーマについて共有したい」と手を挙げて、実際にコンテンツを配信する。そういったアクションが、日常的に行われているのは非常に良い循環だと感じています。
── 学びをサービスとして提供しているスクーだからこそ、社内でも「教える側」になる文化が育っているのですね。
まさにその通りです。そういった姿勢は、現在準備を進めているプロジェクトにもつながっています。
社内で学び合う文化がしっかり根付いているからこそ、それを外に届ける土台もできている。学習プラットフォームをつくる自分たち自身が、学び手であり教え手でもある──この姿勢を大切にしながら、今後の開発組織も進化させていきたいと思っています。
今後の目標・採用
── ここからは、今後の目標や中長期戦略について伺わせてください。代表の森さんからも方向性が発信されているかと思いますが、改めて加藤さんご自身の言葉でお聞かせいただけますか?
私自身が中長期的に目指しているのは、「学習」という行為をもっと多くの人にとって“実用的で価値のあるもの”として届けていくことです。
これまでの自身の体験からも、学ぶことの大切さ、そしてその学びが実際の経験と結びついたときに、どれだけ業務や人生に貢献できるかということを強く実感してきました。だからこそ、スクーのサービスを通じて、より多くの人にその価値を届けられるよう尽力していきたいと考えています。
── そうしたビジョンを実現していく上で、「どのような人と働きたいか」という点についてもお聞かせください。
まず、大前提として「素直で正直な人」と一緒に働きたいという思いがあります。これは職種にかかわらず、あらゆる場面で信頼関係を築くうえで欠かせない要素だと考えています。
そのうえで、私が特に重視しているのは「物事に本気で熱中できる人」。自分が取り組んでいることに対して、“本気を出している”と堂々と言える人。そしてその熱量を、チームや周囲に良いかたちで伝播できる人ですね。そういった仲間と一緒に、サービスを育てていきたいと思っています。
── まさにスクーのカルチャーにマッチする人物像ですね。ちなみに、現在の採用状況についてはいかがでしょうか?
現在も採用活動を進めており、中期的な事業計画に基づいて、今後さらに採用を強化していく予定です。
特にエンジニアの割合は、社内全体でも比較的高く、今後もその比率は大きく変わらないと思います。プロダクトの拡張や新たな挑戦を見据えて、引き続き優秀な仲間を増やしていきたいと考えています