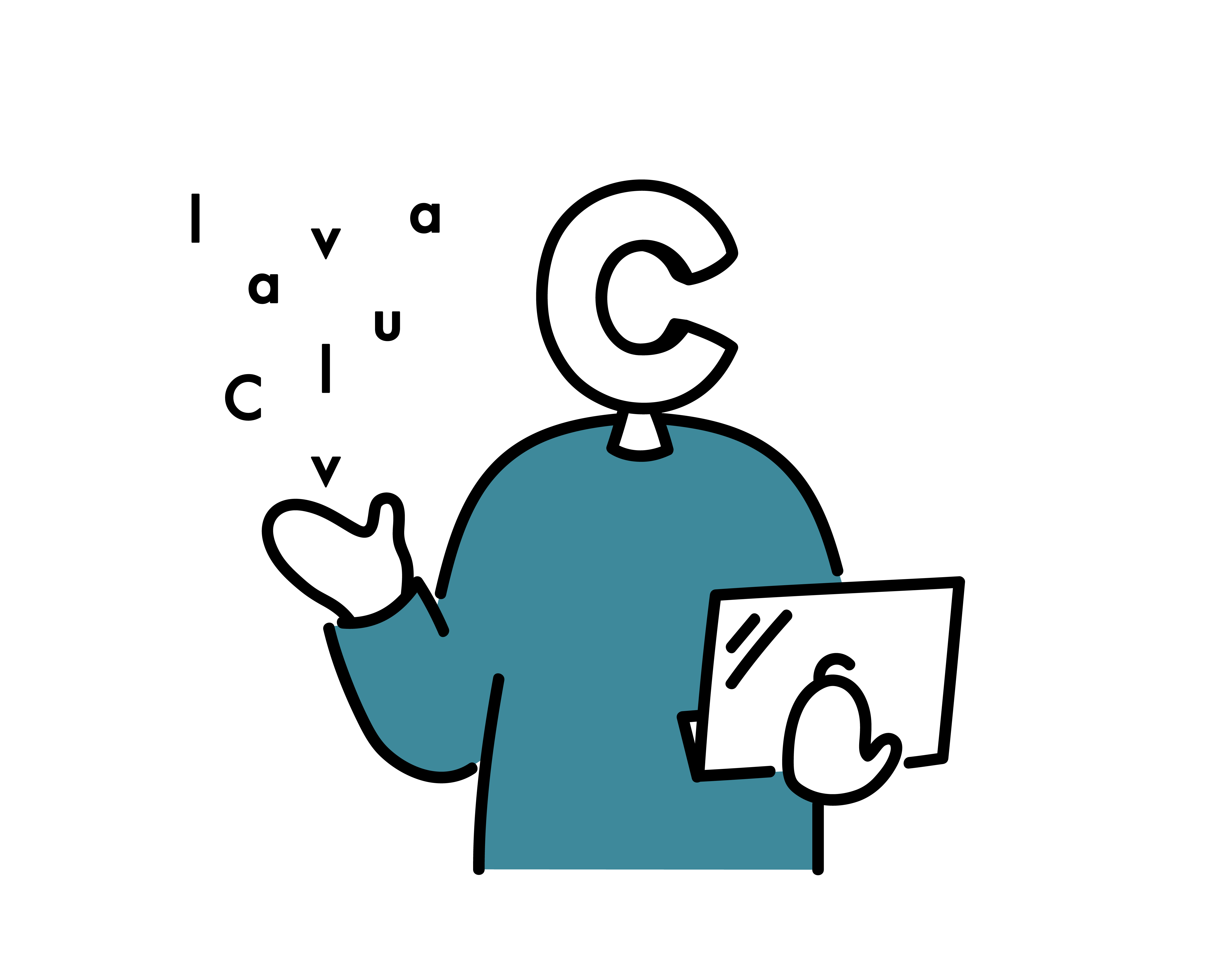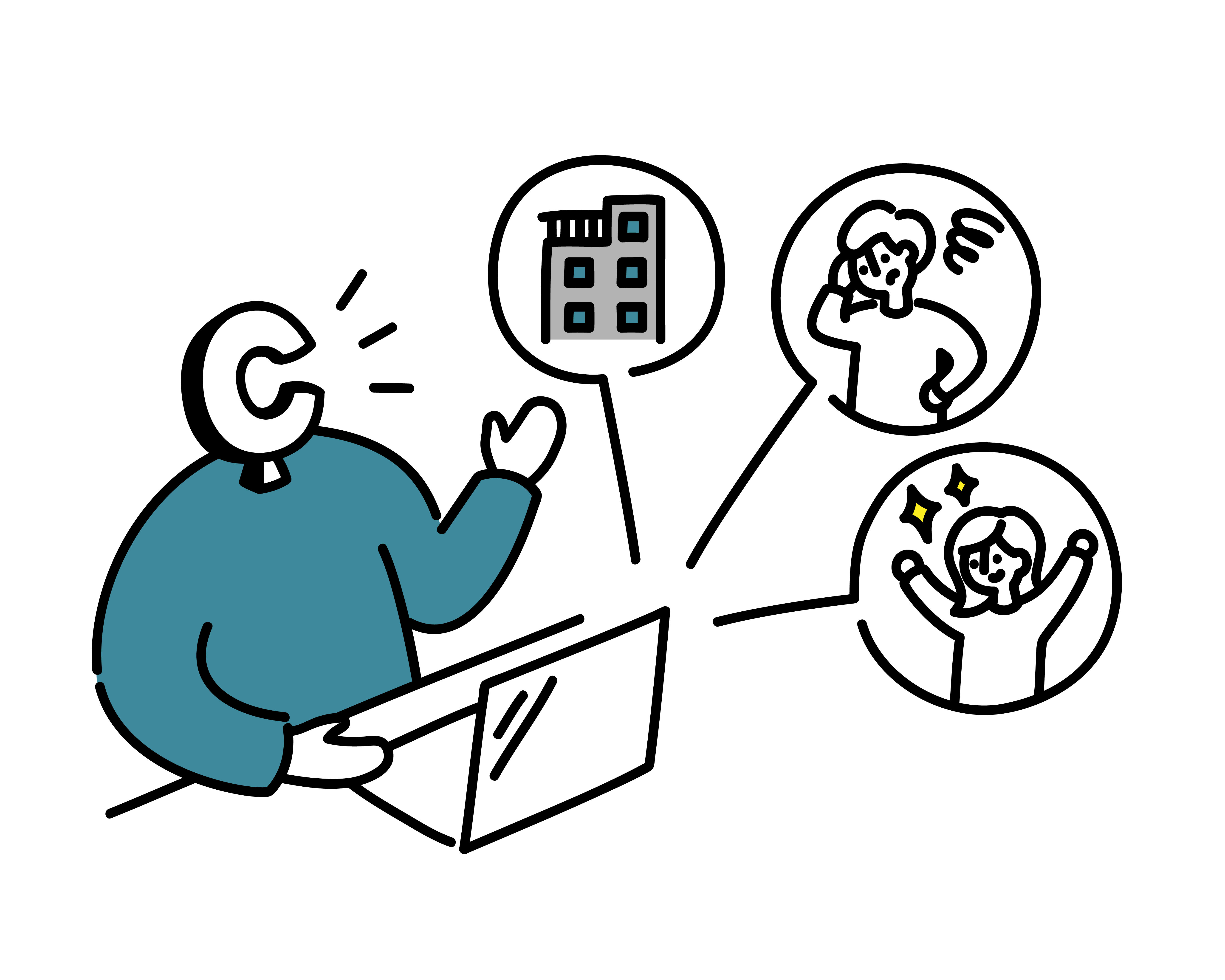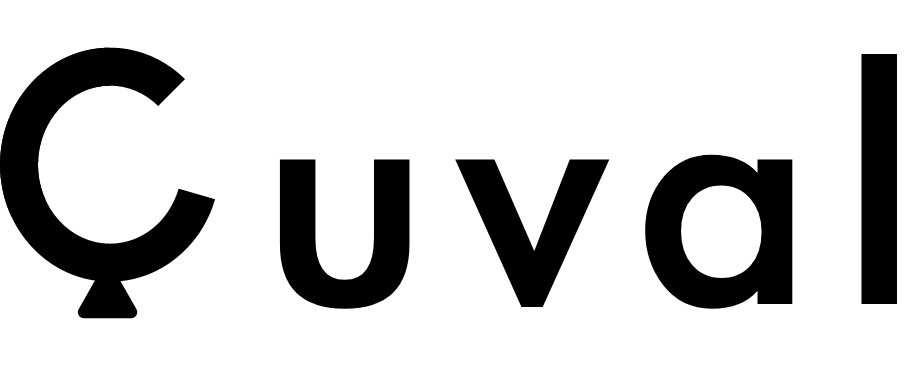西村 成城氏|株式会社Jiffcy 代表取締役CEO
大学在学中より複数のサービス開発に取り組み、2019年に法人を設立。SNSやマッチングサービスなどの事業を展開した後、2021年にテキスト通話アプリ「Jiffcy(ジフシー)」を自ら開発。2023年の正式ローンチ以降、Z世代を中心に急速にユーザーを拡大。現在はCEOとして採用・事業計画・グローバル展開を牽引し、「人類の可能性を解放する」というビジョンのもと挑戦を続けている。
株式会社Jiffcyについて
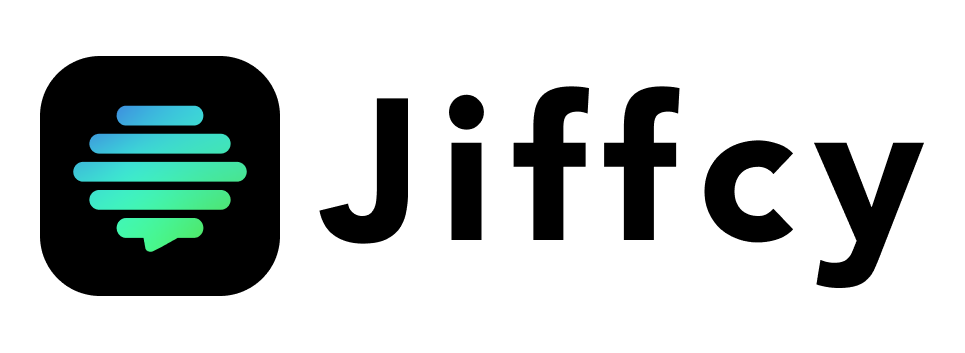
声を出さずに電話ができる──テキスト通話アプリ「Jiffcy」
── 御社の事業内容を教えて下さい。
はい。私たちはテキスト通話アプリ「Jiffcy(ジフシー)」を提供しています。このアプリは“声を出さずに電話をすることができる”という特徴を持っています。
具体的には、まず相手を電話で呼び出し、応答するとトーク画面に移動します。このトーク画面が特殊で、入力された文字が変換される前から、一文字ずつリアルタイムで表示される仕組みになっています。
この2つの機能を組み合わせることで、まるで電話をしているように「相手がその場にいる感覚」をテキスト上で実現できるんです。音声通話には、特有の親密なコミュニケーションがありますが、「声を出す」という点でハードルの高さもあると思います。
一方で、Jiffcyの場合はテキストでありながら音声通話に近い親密度の高いコミュニケーションを可能にします。つまり、テキストの手軽さと音声通話の親密さを掛け合わせた“いいとこ取り”のサービスになっているんです。
西村さんのキャリア

転勤族として過ごした幼少期──新しい環境を楽しむ
── 改めて、どんな幼少期をお過ごしだったのか伺ってもよろしいですか?
小学校1年生の最初までは日本にいましたが、その後シンガポールとタイに渡り、シンガポールで3年、タイで6年、合計9年間を海外で過ごしました。その後はまた日本に帰国しました。帰国後も含めて引っ越しが多く、いわゆる転勤族の家庭でしたね。
そのため、「故郷」という感覚はあまりなく、「自分の故郷はどこなんだろう」という感じでした。ただ、引っ越しのたびに「新しい環境に行ける!」とワクワクしていました。一般的には転校というと涙の別れをイメージされるかもしれませんが、私は「そろそろ転校したいな」と楽しみにしていたほどです。そうした環境で育ったからか、小さい頃から「冒険家になりたい」と思っていました。新しい刺激を求める性格は、この頃に培われたのかもしれません。
── 高校時代は日本で?
はい。高校時代は日本に戻り、大分で過ごした後に東京へ転校しました。
仲間探しから始まった学生起業──覚悟あるメンバーとの出会い
── 大学は日本大学ですか?
そうです。もともと「創業メンバーを集めたい」という目的がありました。そのため、学生数が一番多い大学の方がいろんな人と出会えると思い、日本大学に進学しました。
── 実際に入学してからの仲間作りについて教えてください。
目的が明確だったので、20近くのサークルに入り、いろんな人と話しました。生活の中で「こんなサービスを作りたい」と思えば、仲の良い友達や周囲の人に声を掛け、一緒に取り組んだりしていました。ただ、その多くは自分だけが突っ走ってしまい、結局ついてこられずに離脱していくことが多かったですね。そうした経験を繰り返す中で「人に頼りきりではいけない」と学びました。
── 離脱が多かった中でも、定着したメンバーはいましたか?
はい。COOの小嶋が経営戦略論のゼミの後輩だったのですが、創業のタイミングからずっと一緒にやっています。
── どのタイミングから関わり始めたのですか?
最初は私が大学4年生、小嶋が大学2年生の時です。無料のプログラミング教室を始めた際に関わり始め、最初はお手伝いのような形でした。その後、私が卒業した2019年に小嶋が役員に就任しました。
── 小嶋さんは学生生活を送りながら役員も務めていたのですね。
そうですね。小嶋は面白い存在だと思います。関わる前までは、私を中心に入れ替わりの多いメンバーで活動していましたが、小嶋は違いました。
── なるほど。では小嶋さんを正式なメンバーとして迎えた決め手は?
最初は分からないものです。やっていく中で離れる人は離れていきます。私は本気度を落として人に合わせることはせず、多くの人は自然と離れていきました。その中で小嶋は自然に仕事を続け、本気度も高く、単純に非常に優秀でした。判断基準は「ついてきているかどうか」だけでしたね。
── 正式に「一緒にやろう」と声を掛けたとき、小嶋さんの反応は?
学生のうちに役員を務め、うまくいけばすごいし、うまくいかなくても希少な存在になれる。失うものはないと説明しました。小嶋も「確かにその方がいい」と納得し、経営チームの一員として参加することになりました。
「新卒カード」よりも「学生起業カード」──就職ではなく起業を選んだ理由
── ここで少し前後しますが、大学卒業後に就職せず起業を選んだ理由を教えてください。
もともと自分の会社をやろうと決めていて、Webサービスを作る中で「そのまま会社にしよう」と考えていました。ただ、親は「大丈夫なの?」と心配していました。そこで「就職と同じように稼げればいいのでは?」と説得し、実際に稼げるようになったので納得してもらったんです。
内心では「失うものはない」と思っていました。新卒カードよりも学生起業の方がレアだと考えていました。うまくいけば「天才的」だし、失敗しても希少な存在として良い会社に入れる可能性がある。なので、自分で稼げるようになった時点で、新卒カードを使うメリットは小さいと判断し、就職せずに起業しました。卒業前のタイミングで法人化しています。
SNSからBtoBサービスまで──数々の挑戦と学びの変遷
── では、ここからプロダクトの話に進めていきたいのですが、その前段として「失敗」といいますか、挑戦の変遷についても触れさせてください。会社を立ち上げてからは、どのような歩みをされたのでしょうか。
会社を立ち上げる前は、思いついたものを形にすること自体が楽しくて取り組んでいました。ただ、その延長線上で自分の未来を想像すると、個人開発でたくさんのアプリやWebサービスを持ち、広告収入で生活している──そんな姿でした。それがあまり自分にとってエキサイティングに思えなかったんです。「世界中の人に使われるサービスをつくる」ことや「世界に影響を与えること」はできないのではと考えていた時に、スタートアップという概念に出会いました。短期間で急成長し、世界に広がるプロダクトを生み出せる枠組みがあると知り、法人設立後からはスタートアップの道を歩み始めました。
最初に資金調達をして取り組んだのは「ビフォパ(ビフォーアフターSNS)」です。インスタグラムでは投稿しにくい「ビフォーアフター」を専門に投稿できる場所を提供すれば、人々が価値を共有できるのではと考えました。しかし、これはうまくいきませんでした。その後も複数のサービスを立ち上げましたが、必ずしもSNSにこだわっていたわけではなく、「インパクトがあるもの」「これまでにないもの」を模索していたんです。中には収益が出ていたtoB向けサービスもありましたが、熱量を持てずやめてしまいました。最終的に、今は「世界中の人に使われる可能性のあるコミュニケーション領域」にフォーカスしています。
── サービスの立案は、どなたが担当されていたのでしょうか。
ほとんど私が考えていました。学生時代からアイデアを出し続けていて、アメリカのモデルを日本に持ち込むケースや、価値基準をずらす発想で考えていました。たとえば「スグタノ」というサービス。くらしのマーケットのように業者を選ぶのではなく、品質が保証されていれば誰でも良いと割り切り、エアコン掃除を配車アプリのように「日付とサービスを選べば即依頼」できる形にしたものです。選択をスキップすることで新しい価値が生まれると考えていました。
── 数多くの挑戦を経て、最終的にどのように意思決定をしていたのでしょうか。
重視していたのは3点です。
- 世界中の人に使われるものか
- 実現可能性が高いか
- 自分たちがやっていてワクワクできるか
この3つを基準に点数を付けて、9点満点の評価をしていました。アイデアは本気でやれば3日間で100ほど出せます。その中で点数が高いものから試し、ダメなら次へ進むという流れでした。「ビフォパ」や「Yagura(月額制インフルエンサーマーケティング)」、「第一志望就活(内定辞退防止の採用プラットフォーム)」などはこの方式で進めていました。
市場調査ではなく“自分の欲しいもの”から生まれたJiffcy
── Jiffcyもその方式で生まれたのですか?
いえ、Jiffcyは違います。それまでの発想は「神目線」、つまり市場規模やビジネスモデルを前提にしていました。しかしJiffcyは「自分が欲しい」という感情から生まれたものです。コロナ禍で「電話はハードルが高い」「メッセージはすぐ返ってこない」と感じ、ちょうど良いコミュニケーション手段がないと気付いたんです。LINEや音声通話、ビデオ通話で十分だと思っていたけれど、実際にはまだ隙間があると感じました。そこから生まれたのがJiffcyでした。
2020年末から2021年1月にかけてプロトタイプを自作しました。当時、会社に資金がなく、エンジニアにも報酬を払えなかったので、自分で作ったんです。その後、2021年8月にα版を制作し、紹介制でユーザーに提供。2023年4月に招待制で正式リリースしました。
── 特にZ世代へのアプローチはどのように行ったのでしょうか。
TikTokを中心に展開しました。中高生から大学生までが中心で、私自身も定義次第ではZ世代に含まれる年齢でした。2021年末頃には、一般公開前にも関わらずウェイティングリストに多くの登録があり、手応えを感じていました。
Jiffcy ショートドラマ
プロトタイプから正式ローンチへ──Z世代を中心に拡大
── その後の展開について教えてください。
2024年7月に招待制を終了してから本格的にユーザー獲得を始めました。そこからユーザー数は大きく伸び、Z世代を中心にオーガニック流入が増加しました。さらに、直近でシリーズAの資金調達を実施し、獲得資金はユーザー獲得のために投じています。現在は広告投資を含め、本格的な成長フェーズに入っています。
── これまで苦労された話も伺いましたが、改めてJiffcyに取り組んで「良かったこと」や「自身にとっての意義」を教えていただけますか。
やっぱり人生をかけるに値することに取り組めているという実感があるのが大きいです。すごく充実していますね。以前は仕事をしていて眠くなることもありましたが、今はまったくなく、むしろ睡眠時間を削ってでも取り組みたいと思える。そういうものに巡り合うのはなかなか難しいと思います。転職ではなく、まさに“天職”に取り組めている感覚です。Jiffcyも好調に成長していますし、「これは大きなことになる」というワクワク感があります。失敗したとしても人生をかけた挑戦なので納得できる──そう思えるほど、全力でやれていることが充実感につながっています。
── ありがとうございます。では現在の業務内容について、どのような割合でリソースを割いていらっしゃいますか。
採用に7割、事業計画に2割、そして残りの1割がPRや広報活動です。
── 採用に7割というのは意外でした。先ほどのシリーズAの資金調達はユーザー獲得が目的とのことでしたが、なぜ採用にこれほど注力されているのでしょうか。
ユーザーが急激に増えたことで、いろんな分野で専門知識や経験が足りていない状況になったんです。業務委託でお願いする場合でも、まずこちらが課題を認識していなければなりませんが、その知識が不足している。効率的にユーザーを伸ばすにも、増えた後の内部的な課題に対応するにも、共に考えてくれる人が必要でした。だからこそ「大量採用」ではなく、「この人しかいない」という人材の採用に注力しています。
これまでは固定費を抑えることが最重要でした。SNSサービスは当たれば大きいが、当たらなければゼロになる。そのリスクを恐れて採用を控えてきました。ただ今は手応えを得て、ようやく採用に踏み切れる状況になったんです。

── 改めてJiffcyという事業の魅力についてお聞かせください。
人類史に影響を与える挑戦だと考えています。電話が登場した当初、人々は「急ぎなら会いに行けばいい」「手紙で十分じゃないか」と懐疑的でした。しかし電話は定着し、コミュニケーションを大きく変えました。それから長い間、電話というコミュニケーション方式は大きく進化していません。
今はスマートフォンの普及によって「テキストで電話をする」ことが可能になりました。音声通話の持つハードルを下げ、コミュニケーションを活発化させるテキスト通話は、次の進化だと思います。私たちが存在する前と後で、人々の生活スタイルが大きく変わる──そんな未来をつくれる挑戦であることが、Jiffcyの最大の魅力です。
組織体制と課題──「脳みそを増やしたい」フェーズへ
── では、ここから現在の組織体制について伺いたいと思います。今は何名くらいで、どのような体制で進めていらっしゃるのでしょうか。また、なぜその体制を選ばれているのかもお聞かせください。
現状は、資金調達前の名残もあって40名ほどの規模ですが、そのうち約30名は業務委託です。正社員は数名で、経営陣が4名という体制になっています。
── 具体的にはどのような組織構成ですか?
経営チームは、CEO、COO、CTO、そして社外取締役の4名です。CEOが全体の経営を見ていて、COOはマーケティング、デザイン、ブランディングなど幅広く担当しています。CTOは開発統括を担っています。
その下にマーケティング組織と開発組織があります。マーケティングは広告はほとんど行わず、口コミで広がる仕掛け作りに注力しています。具体的にはTikTokでバズを起こせる人材などで構成されています。開発チームはCTOの飯島のもとに、バックエンド、インフラ、フロントエンドのエンジニアが配置されています。
プロダクトマネジメントに関しては、私が最終的な姿をイメージして進めており、そこにCOOがブランディングの観点を加え、CTOが具体的な実装に落とし込む流れです。ただ、現在の体制には限界を感じています。イメージとしては「行動量に対する脳みそが不足している」という状態で、もっと“脳みそ”を増やしたいと考えています。
── 今、特に優先されているポジションはPMでしょうか?
はい、PMは非常に必要としています。望ましいのはテック観点を持ったPMですが、必ずしもそうでなくても、経験豊富で自分の判断を信じて動ける方であれば問題ありません。
── 現在の組織について、良い点や課題点を改めて伺ってもよろしいですか。
良い点としては、やはりコアメンバーの結束が非常に固いことです。4名は2019年から一緒にやっていて、Jiffcyのためだけに集まったのではなく、「世界中の人に使われるものをつくる」という共通の目的のために、これまで収益性のあるサービスも捨ててきました。そうした理解を持っているメンバーなので、空中分解することはほとんどないと思っています。
また、業務委託のメンバーもJiffcyを信じて集まってくれている人が多いです。プロダクト自体が尖っている分、その魅力に共感して団結している点も組織の強みだと感じています。
一方で課題は、まさに先ほどお話ししたとおり、コアとなるメンバーの数が不足していることです。今後さらに組織を成長させていくには、そこを補強していく必要があります。
── 現在の組織では、具体的にどのようなことに取り組まれているのでしょうか。
大きく分けると「ユーザーを増やすこと」と「プロダクトを磨くこと」の2点です。その先にあるのは「音声通話の大半を置き換えていく」という目標ですね。
プロダクトを改善することでユーザーが他のユーザーを誘いやすくなりますし、ユーザーが増えれば増えるほど継続率も高まることが分かっています。ですので、「ユーザーがユーザーを増やすこと」が正義だと考えています。マーケティングチームは直接的にユーザーを増やす活動を、エンジニアチームはプロダクト改善によってユーザーを増やす活動を行っています。
── ありがとうございます。プロダクト改善についてお聞きしたいのですが、改善点はユーザーからの声が多いのでしょうか。それとも自分たちで数値を見て判断することが多いのでしょうか。
ユーザーからの声は非常に多く上がってきています。ただし、それをすべて受け入れているわけではありません。あくまで私自身がヘビーユーザーであることから、「自分が本当に使うのか」という観点を重視しています。これはある意味で“超深いユーザーインタビュー”に近い感覚だと思っています。
例えば「知らない人とマッチングして話せるようにしてほしい」という要望は多いですが、私は「知らない人と話しても楽しくない」という感覚なので採用しません。むしろその機能を入れることで、親しい人との利用が減るのではと考えています。そういった理由から「自分を信じる」という判断基準で進めています。
もちろん、一定数のユーザーから直接アイデアをいただくこともあります。それをアイデアリストとして受け取りつつ、自分たちが目指す領域に沿うものを選び、磨き上げています。
目標と採用
── 改めて、今後の目標について伺わせてください。短期的でも中長期的でも構いません。
短期的には「音声通話の大半をテキスト通話に置き換えていく」ことを目指しています。音声通話の約2割は相手の声を聞きたいなど“声が必要な理由”によるものですが、残りの8割は「今すぐ返事がほしい」「複雑な話をしたい」といった理由で、これはテキスト通話で十分に置き換え可能だと考えています。利便性が高く、楽な手段があれば必ず人はそちらを選ぶはずです。
テキスト通話に置き換えることで、コミュニケーション総量を人類単位で1.1倍にでも増やすことができれば、新しいひらめきや発見が生まれやすくなります。これは人類の進歩そのものに直結すると考えています。私たちのビジョンは「人類の可能性を解放する」。その土台にあるのはコミュニケーションであり、それを活発化させることで文明の進むスピードを格段に上げたいんです。
── ありがとうございます。その上で、どのような人と一緒に働きたいと考えていますか。
大前提として「人類の可能性を解放する」というビジョンに共感してくださる方が理想です。ただ少し抽象的なので、まずは「Jiffcyに大きな魅力や将来性を感じる」という方と一緒に働きたいですね。
また、最近は出社文化に切り替えており、オフィスで密度高くワイワイやりたい方を求めています。
── より具体的には、どのようなポジションを特に求めているのでしょうか。
最も必要としているのはPMです。特にテックの観点を持つPMが望ましいですが、経験豊富で自分の判断を信じられる方であれば問題ありません。加えて、CMOも求めています。これまでお金を使ったユーザー獲得を行ってこなかったため、今後はテレビCMなどを含め、投資を前提にユーザーを伸ばしていきたい。その戦略を担える方が必要です。
さらにCFOも探しています。資金調達を私ひとりで続けるのは難しく、共に取り組んでくれる方を求めています。そして最も重要度が高いのが「CUSO(Chief U.S. Officer)」です。アメリカ市場を押さえることができれば、他の市場で競合が出ても買収して対応できますが、アメリカを取れなければ世界シェア1位は難しい。日本で成功しても、結局は2位や3位で終わる可能性が高い。だからこそ今、アメリカ市場を担うリーダーが必要なんです。
── つまり世界を見据えた事業展開をされている、という理解で合っていますか。
はい、その通りです。Jiffcyはすでに日本以外の国でも使われています。ユーザー数で見ると、日本が最も多く、次いでアメリカ、韓国という順になっています。
── なるほど。日本だけをターゲットにしているわけではなく、グローバルを視野に入れているのですね。
はい。アメリカ市場を抑えることを最優先に考えています。これまで自分たちだけで走り続けてきましたが、今後は専門性を持つ人材を迎え入れ、組織をより強固にして成長を加速させていくフェーズに入っています。