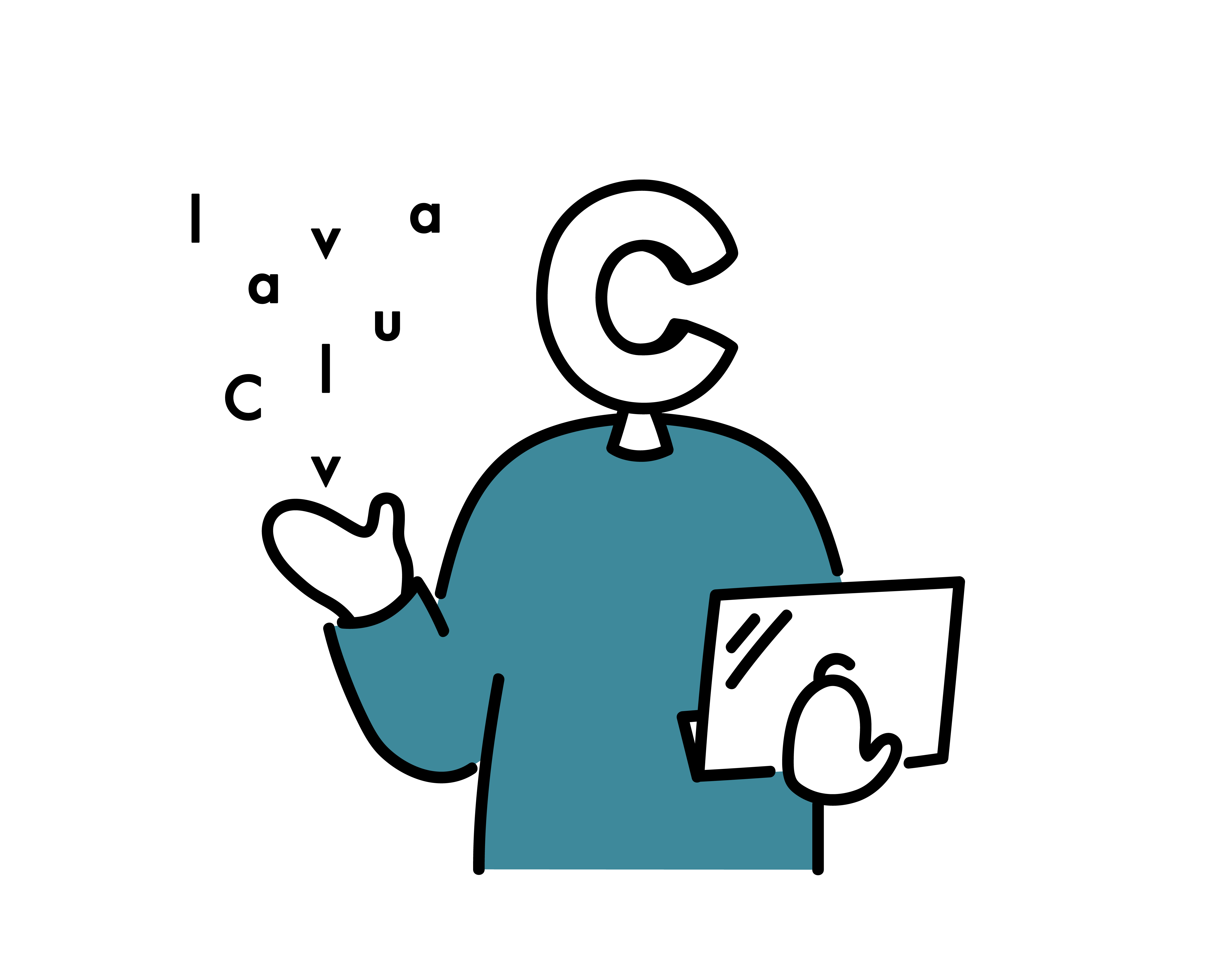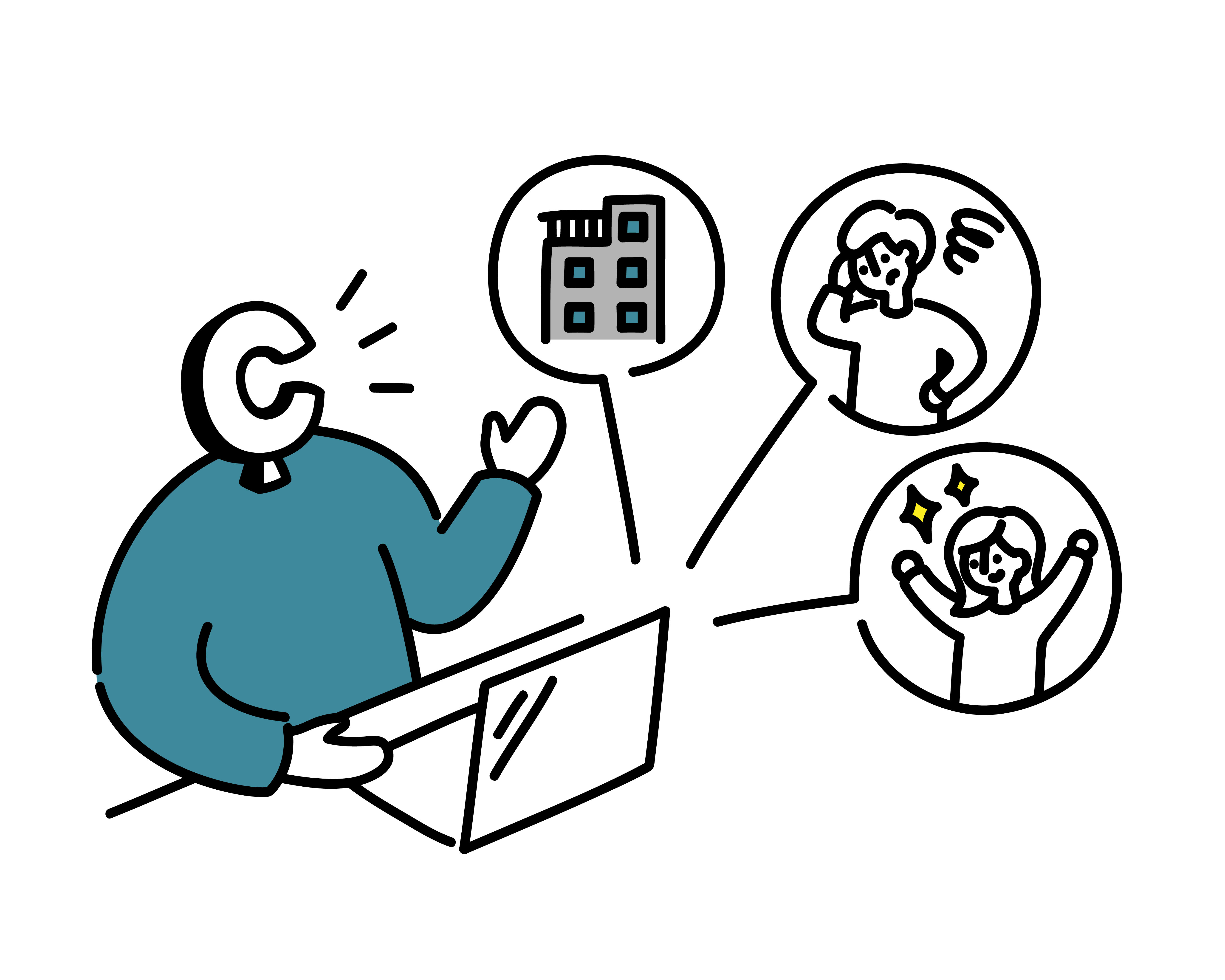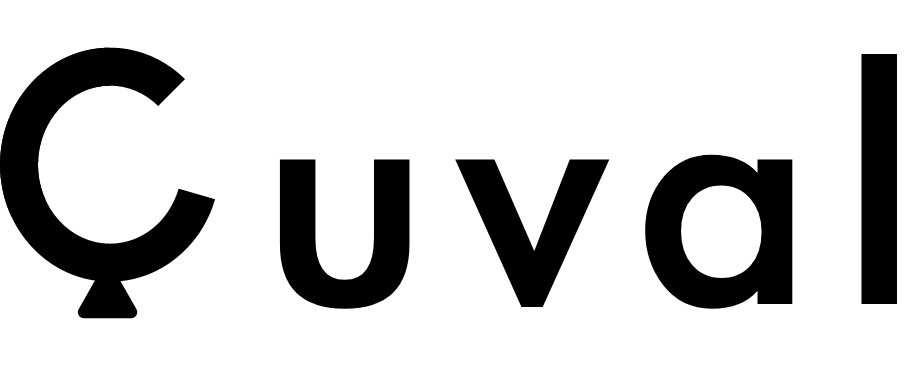飯田 康介氏|SecureNavi株式会社 技術本部長
SIer・Web系スタートアップなどを経て、複数社でCTOやVPoEを歴任。2022年にSecureNaviへ入社し、セキュリティと経営の両視点から技術戦略を牽引。現在は「セキュリティファースト」と「AI共創」を掲げた開発組織づくりに注力している。
SecureNavi株式会社について
── 御社の事業内容を教えて下さい。
私たちSecureNaviは、情報セキュリティ領域におけるクラウドサービスを開発・提供している企業です。一般的に情報セキュリティと聞くと、ウイルス対策ソフトやログ分析、システム開発といった、技術寄りの領域を想像される方が多いかもしれません。しかし私たちはそれとは少し異なり、企業の“組織的な情報セキュリティ体制の強化”を支援するサービスを展開しています。つまり、文系・非エンジニア領域に近いセキュリティ支援と言えるかもしれません。
現在、新規事業も含め4つのプロダクトを開発しており、主力となっているのは、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証とプライバシーマーク(Pマーク)取得支援です。さらに近年では、ISMSのクラウドセキュリティ対応にも力を入れています。
ISMSやPマークは単に取得すればよいというものではなく、適切に運用することで、企業全体の情報セキュリティレベルが大きく向上するという特長があります。私自身、前職のエンファクトリーでISMSの認証取得を経験しましたが、認証を得ているという事実自体が、サービスの信頼性を高め、ビジネスの後押しになることを実感しました。
たとえば近年、企業の活動において、セキュリティ面のチェックが非常に厳しくなっています。その中で、ISMSやPマークを取得していることは、「きちんと管理されている会社だ」という評価につながりやすい。つまり、情報セキュリティへの取り組みが、売上や契約獲得に直結する時代になってきているのです。
私たちSecureNaviが目指しているのは、まさにその考え方を前提とした世界――
「セキュリティに取り組めば売上が上がる世界」を実現することです。
現在はISMSやPマークを中心に事業を展開しながら、さらに他のセキュリティ領域にも順次取り組みを広げています。
飯田さんのキャリア
── ではここから、少し時間をさかのぼってキャリアの原点を伺わせてください。幼少期から高校・大学時代まで、どのような環境で育たれたのでしょうか?
かなり昔のことなので記憶もあいまいなんですが(笑)、子どもの頃は控えめで、おとなしい性格だったと記憶しています。周囲からも「真面目だね」と言われるタイプだったと思いますね。
中学ではバレーボール部に所属していましたが、それ以上にテレビやアニメが好きで、ジャンプ黄金期の『スラムダンク』なんかを夢中で見ていた時代でした。
一方で、父が電気関係の仕事に就いていた影響もあり、当時から無意識のうちに理系分野への興味が育まれていたように思います。自然と理系科目に親しみを感じていて、高校でも理系コースを選び、大学も電気電子系に進学しました。
── 大学では、どのようなことを学ばれていたのでしょうか?
専攻は電気電子工学で、情報系というよりは、“オームの法則”に代表されるような電気の基礎理論や強電系の技術が中心でした。配属された研究室では、雷が電子機器に与える影響を計測するための装置開発といった、かなりニッチで専門的なテーマに取り組んでいました。
同級生たちは東京電力や古河電工、九州電力、北陸電力など、電力・重電系の企業に進む人が多かったですね。
でも、私の転機になったのは研究室の教授の趣味的な活動でした。その先生は本当にものづくりが好きで、自作PCを組み立てたり、研究室内のネットワークやメールサーバー、Webサーバーを構築したりといったことを学生にも実践させるようなタイプだったんです。
なぜか私がすべてを担当することになり、ネットワークやメールサーバー、Webサーバーを構築することを一から学び、実際に作業していく中で、「これを仕事にできたら面白いかもしれない」と心から思うようになったんです。
そこから「この分野の職種ってなんだろう?」と調べていった結果、たどり着いたのが“システムエンジニア”という職業でした。
── 大学卒業後は、どのようなキャリアを歩まれたのでしょうか?最初からエンジニアとしての道に進まれたのですか?
はい。大学卒業後、最初に就職したのはメーカー系のSIerでした。当時はまだIT業界が今ほど注目されていなかったこともあり、「研究室で学んできたことを活かせる仕事は何か」と考えた結果、自然とその道を選んだという感じです。
周囲の友人たちは研究室経由で就職などに進んでいきましたが、私は自力でリクナビなどを使って就職活動をしていました。
入社後はまず3ヶ月ほどアプリケーション開発に関する研修を受け、その後は日立水戸の工場に配属となりました。配属先では社内向けの在庫管理システムなど、ブラウザを活用したシステム開発に関わることになり、「ブラウザを使って業務を効率化する」という概念に初めて触れたのもこのときです。業務を通じて、「こういうシステムがあるんだ」と、手を動かしながら実践で学ぶ日々でした。
── その会社にはどれくらい在籍されていたのでしょうか?
在籍期間は2年です。その後、別の会社を1社挟んでから、カービューに入社しました。
── カービューには長く在籍されていたと伺っています。
そうですね。カービューには約7年間在籍しました。この時期が、自分にとっての“ITキャリアの本格始動”だったと感じています。
実はその前に入った会社は不動産系の企業で、社内SEのようなポジションだったんです。ただ、そこでの業務は自分がやりたかったこととは少しズレていて、「やっぱりWebサービスに関わりたい」という気持ちが強くなっていきました。
改めて転職活動をしていく中で出会ったのがカービューでした。当時はまだ上場前で、これから大きくなっていきそうなフェーズにありましたし、面接のなかでインフラ周りにも触れられる環境があると聞いたことで、「ここなら裏側まで広く関われる」と確信しました。
もともとクルマそのものに強い関心があったわけではありませんが、F1などのモータースポーツには興味がありましたし、「この分野でWebサービスに挑戦するのは面白いかもしれない」と思ったのが入社の決め手でした。
── ここからは、カービュー以降のキャリアについてお伺いします。さまざまな企業や立ち上げに関わってこられていますが、それぞれどのような経緯で意思決定をされたのでしょうか?
そうですね、振り返ってみると、明確なロールモデルが周囲にいなかったことが、自分のキャリアに大きな影響を与えていたと思います。もうすぐ48歳になりますが、IT業界では年齢的にも上の方ですし、正直なところ、どうキャリアをつくっていけばいいのか悩んでいた時期がありました。
終身雇用が崩れたと言われる時代のなかで、「同じ会社に居続けることのほうがリスクではないか」と感じていた一方で、転職に対して良いイメージがあったわけでもなく、葛藤を抱えていた時期もあります。
カービューで約7年間、さまざまな経験を積んだあと、退職のきっかけになったのは、元同僚から起業への誘いを受けたことでした。「一緒にやろう」と言われて思い切って飛び込んだものの、実際には資金調達が難航し、すぐに「やっぱり無理だった」と言われ……。しかも当時、ちょうど結婚式の直前で、スピーチもその方にお願いしていたという(笑)。結果的には急遽代役を立てて、無事に式は終えたものの、路頭に迷ってしまいました。
── そこからオールアバウトへの入社につながったのですね。
はい。ちょうどそのタイミングでご縁があってオールアバウトに入社しました。カービューやこれまでの経験が評価され、リーダーとして参画することができました。その後しばらくして、「もう一度スタートアップのような環境で挑戦したい」と思うようになり、セプテーニ・ベンチャーズに転職しました。
セプテーニでは、社内起業制度のような仕組みがあり、事業プランを持った人がチームを結成してスタートアップのように事業を立ち上げる仕組みがありました。たまたまそのタイミングで事業責任者の方と出会い、「カービューやオールアバウトでの経験が活かせる」と声をかけてもらったんです。
これまで、リーダー的な立場は何度か経験していましたが、プロダクトのトップとして全責任を持って推進するのは初めてでした。「ここでの経験は確実に自分を成長させる」と思い、飛び込みました。
最終的に事業自体はセプテーニに譲渡され、私は社内で広告入稿システムの開発を担当することになりました。このときに、ドメイン駆動設計やスクラム開発など、モダンな開発プロセスを初めて本格的に経験し、エンジニアとしての基礎が固まったと感じています。
── その後はクラウドワークスに移られたと。
はい。もともと社外向けのサービスで価値を提供したいという思いが強くあったので、ご縁があってクラウドワークスに入社しました。チームリーダーとして参画し、しばらくしてマネージャーの打診も受けていました。
ですがちょうどその頃、以前関わった教育系アクセラレーターの知人から「一緒に立ち上げないか」と再度声をかけられたんです。以前に少し相談に乗っていた縁があり、「ぜひもう一度」と言われてしまって。悩んだ末にクラウドワークスを離れ、再びチャレンジしましたが……またしても資金調達が実現せず、プロジェクトは終了となりました。
── そこからバリュース、そしてCTOロールへとつながっていくんですね。
そうです。ちょうどその頃、バリュースからスカウトを頻繁にいただいていたので、お話を聞いてみたところ、レガシーなシステムのリプレースが急務という課題があり、モダンな環境への刷新に取り組めそうだと感じました。
そこで、CTOとして約1年半かけて、ドメイン駆動設計やスクラム導入による全面リプレースを実施しました。人生で初めて自分が中心となって技術方針・組織設計をリードした経験だったので、非常に大きな意味を持つ時間でした。
ただ、プロジェクトが一区切りついた頃には若干の燃え尽き症候群もありましたし、バリュース自体がどちらかといえば中小企業寄りの文化だったこともあり、もう少しチャレンジングな環境に行きたいと考えてIROYAにジョインしました。
── IROYAではVPoEとしても活動されていたんですよね。
はい。ちょうどそのタイミングで事業が再編され、Monoposに切り替わる形になったんですが、ここではVPoEとしてエンジニア組織づくりに本格的に関わることができました。
採用、人事制度設計、バリュー策定、評価制度、リモートワークの導入など、バックオフィス領域まで幅広くカバーしました。第一子が生まれる時期でもあったので、「リモートを前提とした働き方」を制度として整備したのも印象的な経験です。
最終的に事業が凸版印刷に買収され、プロダクトもクローズすることになったので、そのタイミングで次のステップを考え、エンファクトリーに入社しました。
── エンファクトリーではCTOとして、どのような役割を担われていたのでしょうか?
エンファクトリーでは組織文化づくりから技術戦略まで、全体的な統括を任されていました。もともとオールアバウトからの分社化という経緯があり、オールアバウト時代から私のことを知っていた方々とご縁が再びつながった形です。
エンジニアとデザイナーで構成される“クリエイティブユニット”の立ち上げにも関わり、横断型で動ける体制づくりに取り組みました。過去の経験を活かして、組織設計・技術環境・文化形成の三本柱を支える役割を担うことができました。
── ここまでの経歴を拝見すると、本当に“ロールモデルが存在しない”キャリアの築き方ですよね。
そうですね(笑)。でも、それこそが自分らしいキャリアの形なんだろうなと、今では思っています。
── ここまでのキャリアの中で、特に印象に残っている出来事や出会いがあれば教えてください。
やはり一番印象に残っているのは、カービューに在籍していた頃の経験ですね。初めて本格的にIT業界の現場に飛び込み、Webサービスの開発・運用に深く関わることができたという点で、自分にとっては非常に大きな転機だったと感じています。
当時はちょうど、Yahoo!をはじめとする各種Webサービスが急成長していた時期で、世の中がどんどん便利になっていく一方で、「この便利さは、どうやって裏側で支えられているんだろう?」という好奇心がありました。
もちろん、自宅でもLinuxサーバーを立てたりして少しは触っていたんですが、カービューの現場で見た“本物のスケール感”はまったく別物でした。たとえば、月間トラフィックが5億PVを超えるような大規模なサービスをどうやって支えているのか。実際に現場に入ってみると、ラックいっぱいに並んだサーバー群、冷えたデータセンターの空気感、冗長構成されたネットワーク……どれもが新鮮で、驚きの連続でした。
「こうやって落ちないサービスがつくられているんだ」と、まさにWebの“裏側”を初めてリアルに体験できた瞬間でしたね。
このときに得た知識や感覚は、その後どの現場に行っても確実に活きましたし、自分のエンジニアとしての原体験として今も強く残っています。
── 飯田さんのプロフィールには、「創業メンバーとしてのプロジェクト参画」や「地元コミュニティへの貢献」など、今後チャレンジしてみたいことが書かれていましたが、改めてその想いを伺ってもよろしいでしょうか?
そうですね。まず創業メンバーとして何かに関わるというのは、過去にも何度か挑戦の機会がありましたが、タイミングやご縁が重ならなかった部分もあって、実現には至りませんでした。
ただ、「本当に最後のチャレンジ」という意味で、もう一度トライしてみたい気持ちはまだどこかにあります。とはいえ、家族との相談も必要になりますし、すぐにというわけではないですが、ご縁があれば本気で向き合ってみたいと思っています。
── 「地元へのIT貢献」についても、強い想いをお持ちなんですね。
はい。現在は埼玉県の川越市に住んでいるのですが、地元ではまだまだITの力を活かせる余地が多くあると感じています。地域に根ざした取り組みとして、ITによる支援や連携を生み出していけたらという想いは強く持っています。
ただ、今はなかなかきっかけが掴めていないのが正直なところです。例えば商工会議所の青年部のような地域組織にフリーランスとして参加できると聞いたこともありますが、「どうやって入ればいいのか」「どこからアプローチすればいいのか」と、模索中という段階です。
とはいえ、最終的には今住んでいる地元に根差した社会貢献をしていきたいという思いは確実にあって、それはこれからの人生の後半に向けた大切なテーマでもあります。
── ITによって変わったご自身の人生経験が、そうした想いにもつながっているのでしょうか?
それは間違いないですね。
私が学生や社会人になりたての頃は、Googleも使えなかった時代でした。調べ物をしようにもインターネットに頼れず、本を探すしかありませんでしたが、欲しい専門書は地元の本屋には置いていない。東京に出て、紀伊國屋でやっと手に入れる……そんな時代だったんです。
それが今では、検索すれば情報にすぐ辿り着ける。遠隔でも学べる。仕事もできる。ITの発展によって、生活も、学びも、仕事のスタイルも劇的に変わりました。
だからこそ、ITの可能性は本当に大きいと信じていますし、自分自身が実感してきた“便利になった社会”を、今度は誰かに届ける側に回りたいという気持ちがあるんです。
「ITで世の中を良くしたい」──その漠然とした想いが、自分のキャリア全体を通して一貫して根底に流れているものなのかもしれませんね。
SecureNaviとの出会い
── ここからはSecureNaviでのお話を伺っていきたいと思います。まずは、入社のきっかけについて教えていただけますか。
正直に言うと、当初は転職自体まったく考えていなかったんです。ちょうど採用関連の情報を整理していたタイミングで、「せっかくだから」と久々にWantedlyを開いたんですね。すると、SecureNaviの代表・井崎から届いた1通の長文メッセージが目にとまりました。
読んでみたら、ものすごく熱量のある内容で、その熱意に思わず惹かれてしまったのが最初のきっかけでした。
── 実際にお話をされたときの印象はいかがでしたか?
最初は軽い気持ちでカジュアル面談に参加したんですが……気づけば、予定していた時間の倍以上、2時間半以上話し込んでいたと思います。それくらい、話していてお互いの考えや課題意識に共通点が多くて、強く共感したのを覚えています。
特に印象的だったのが、ISMSやPマークの運用に対する課題意識です。私自身、前職のエンファクトリーでISMSの認証取得を自分で主導していたことがあり、そのときの苦労やジレンマがあったんですね。
最初は外部のコンサルにお願いして何とか形にはなったものの、その後の運用がとにかく大変で……。ExcelやWordでの対応には限界を感じましたし、「これって本当に会社の情報セキュリティ向上につながっているのか?」と、疑問と苦しさのなかで委員会活動を続けていたのが正直なところです。
── ご自身の実体験とSecureNaviの事業が強くリンクしていたわけですね。
まさにそうです。井崎の話を聞いて、「これはまさに自分が苦しんだ課題に真正面から向き合っているサービスだ」と感じましたし、自分の経験を活かせるフィールドがここにあると直感的に思えました。
ただ、当時はちょうど子どもが生まれた直後ということもあり、転職には慎重になっていたんです。でも、妻に相談したところ、「今までの働き方を見ていたら、ここは挑戦してみたらいいんじゃない?」と、あっさり背中を押してくれて。
加えて、育児との両立を気にして「半年ほど入社を遅らせられませんか?」と井崎に相談したら、「育休使えばいいじゃないですか」と即答してくれて……。その柔軟さも含めて、「ここなら本当にやっていける」と思えたんです。
また代表の井崎がエンジニア出身で、サービス自体を自ら一人でつくり上げたという点が大きかったです。エンジニアリングへの理解が深い代表のもとで、同じ視座でサービス開発に向き合える。これはこれまでの経験の中でもなかなか出会えなかった要素でしたし、自分の中でひとつのキーワードでもあったので、まさに“ドンピシャ”だったと思っています。
SecureNavi 入社後
── SecureNaviに入社されてから、まずどのような業務に取り組まれましたか?
明確なミッションが最初から与えられていたわけではなくて、自分で考えながら動いていくスタイルでしたね。というのも、私が入社した直後に育休に入らせてもらっていて、実際に復職したのは半年後のタイミングでした。SecureNaviではパラシュート人事のようなことはせず、育休明けも一人のメンバーとしてスタートしたという形です。
ただ復職してすぐに、「HerokuからAWSへのインフラ移行をやってほしい」という話がありまして。もともと一部のDBはAWSにあったのですが、サービス全体としてはHerokuをメインに使っていたんです。それを全面的に移行する必要が出てきたんですね。復職してから約1ヶ月半ほどで全て移行するという、かなりタイトな初仕事でした。
その後、2023年10月に技術本部長に正式に就任しています。
── 実際に復職されたのはいつ頃だったんでしょうか?
2022年12月に入社し、そこから育休を取得。2023年7月に復職して、9月末ごろから本格的に体制整備に入り、10月に技術本部長に就任しました。
── 入社後、特に苦労されたことは何でしたか?
一番はやはりエンジニア採用ですね。
当時、エンジニア採用の経験者が社内におらず、カジュアル面談からスクリーニング、選考フロー設計、メール対応まですべて自分でやっていました。同時に部門長としてミーティングにもフル参加していたので、日中はほぼ会議で埋まっていました。夜に採用業務を進めることも多かったです。
また、本部長でありながら部長ロールも兼務していたため、メンバーのマネジメントも担っていました。人が増えるまでの期間は、本当に大変でした。
── 当時のエンジニアチームはどのような規模感でしたか?
入社当時、会社全体の社員数は約15名、エンジニアはたった2名ほどでした。まさに立ち上げフェーズで、仕組みづくりや採用、体制構築をゼロから進める必要がありました。
── 逆に、「入社して良かった」と感じた点はありましたか?
まずは働き方の柔軟さですね。SecureNaviはフルリモート・フルフレックス制度を採用していて、子育て世代との相性がとても良いです。私自身もまだ子どもが小さいので、保育園や幼稚園からの急な呼び出しにも柔軟に対応できる環境は本当にありがたく、働きやすさは抜群です。
もう一つは、情報セキュリティという領域に本格的に関われていることです。これは自分自身のスキルアップにもつながりますし、SecureNaviとして「情報セキュリティへの取り組みが売上に貢献する世界をつくる」という大きなビジョンにも直結しています。
世の中から情報漏洩などの悲報をなくすためのプロダクトを支えるという意義のある仕事に関われている実感があり、そこに面白さとやりがいを感じています。
── 現在、飯田さんご自身の役割について伺いたいです。どのような業務を担っていらっしゃいますか?
現在は技術本部長としてのマネジメントを中心に、中長期の技術戦略の策定に注力しています。直近では、会社全体の事業計画が大きく動いたタイミングもあり、それにあわせて技術面からどう支えるかを構想・実行していくことが主なミッションになっています。
全体的な業務の割合で言うと、技術戦略が約5割を占めていて、残りの3割ほどはブランディング活動にあたっています。
SecureNaviはまだまだ知名度が高いとは言えないフェーズにあり、採用においてもブランディングが重要だと考えています。その一環として、エンジニア向けのテックブログの立ち上げや、「テックバリュー」と呼ばれる、社内でエンジニアリングに特化した価値観の言語化などにも取り組んでいます。
また、AI関連の領域にも並行して関わっており、現在はプロダクトへのAI組み込みを進めている技術戦略室の室長も兼務しています。社内の開発生産性を高めるためのツール活用(たとえばCursorなど)にも取り組んでおり、現場の改善も継続的に進めています。
採用については、カジュアル面談から一次選考までは部長やリーダー陣に任せ、最終面接以降を自分が担当する体制を敷いています。割合としては全業務の1割程度になりますが、候補者の価値観やカルチャーフィットを丁寧に見ていくフェーズとして、大切にしています。
── 改めて、SecureNaviという事業の魅力を、飯田さん自身はどのように感じていますか?
「日本国内で初めて、セキュリティコンプライアンスという新しい市場を開拓している」という点に、非常に大きな可能性を感じています。
多くの人が“セキュリティ”と聞いてイメージするのは、ウイルス対策ソフトやファイアウォール、ログ分析といった、いわゆる理系的なセキュリティだと思います。ただ、SecureNaviが注力しているのは、そうした“システムのセキュリティ”ではなく、組織構造や運用体制に焦点を当てた“文系のセキュリティ”です。
この分野では、たとえばISMSやPマークなどの認証を取得し、それをしっかりと運用することで、結果的に顧客や取引先からの信頼につながり、売上にも貢献するという仕組みが成り立ちます。
海外ではすでにユニコーン企業も生まれている市場であり、日本でも今後必ず成長する分野だと確信しています。このように、まだ誰も本格的に手をつけていない領域にチャレンジできるという点が、SecureNaviで働くことの大きな魅力ですね。
現在の組織について
── 入社当初は2~3名規模だった開発組織も、今ではかなり拡大されていると伺いました。現在の体制について教えてください。
現在、SecureNavi全体の社員数は90名を超える規模になりました。私が入社した当時は15名ほどでしたので、まさに景色が変わるほどの急成長を実感しています。エンジニアに限っても、業務委託を含めると22名規模にまで拡大しており、当初と比べて約3〜4倍の組織規模になりました。
技術本部の中では、大きく4つの部署に分かれています。1つ目が私が管掌する「技術戦略室」で、新しい技術の導入検証や中長期の技術戦略の立案を担うチームです。2つ目が「基盤開発部」で、SecureNaviや今後立ち上がる複数のプロダクトのインフラやセキュリティ領域を横断的に支える、いわゆるSRE部門にあたります。3つ目が「プロダクト開発部」で、SecureNaviのロードマップに基づいた機能開発を中心に、顧客価値を直接届ける役割を担っています。そして、4月には新たに「プロダクトデザイン部」も立ち上げ、組織としての領域分担と専門性の向上を図ってきました。
── 現在、開発組織として特に注力している取り組みはどのようなものでしょうか?
まずは、外部への発信強化を意識しています。テックブログの開設に加え、登壇機会の拡充や外部企業とのセミナー共催など、社外に向けた情報発信を積極的に始めています。そういった対外発信の土台として、社内での「技術戦略」や「テックバリュー」の言語化も進めており、SecureNaviの開発組織としての立ち位置や考え方を明確に示せるような準備を進めています。
── 急拡大された中で、組織としての「良いところ」と「課題」についてもお聞かせください。
良い点としては、採用時にカルチャーフィットを何よりも重視していることもあり、プロダクト愛が強く、プロダクト志向のメンバーが多い点が挙げられます。開発を進める上で、なぜこの機能が必要なのか、顧客にどんな価値を届けるのかという議論が自然と生まれる文化が根づいているのは、大きな強みだと感じています。
一方で課題としては、長らく少数精鋭体制だったこともあり、個の力に依存した働き方がベースになっていたという点です。現在のように組織が3倍規模になると、2人で完結していた開発プロセスや判断基準では回らなくなる場面が増えてきました。いまはまさに「個からチームへ」シフトするフェーズにあり、チーム単位での最適化に向けたプロセス整備や意識づけに取り組んでいるところです。
── SecureNaviではフルリモート・フルフレックスという柔軟な勤務体制を採用されていますが、その中でどういった工夫をされていますか?
まず、SecureNaviの文化として「ドキュメントをしっかり残す」という点は徹底しています。特定のメンバーがその場にいなくても業務内容が把握できるよう、文字情報だけでなく、必要に応じて動画を残すなど非同期コミュニケーションが可能な体制を整えています。
また、ハドルやGoogle Meetを活用して、いつでも気軽に質問できる環境も意識的に作っています。ペアプロやモブプロも積極的に取り入れており、時間が合うタイミングで一緒に開発しながら学び合える機会を増やしています。
さらに、エンジニアの定例会では意図的に雑談の時間を設けるようにしています。特にフルリモート環境では業務外の会話が減りがちですが、あえてブレイクアウトルームで自由に話せる時間を設けることで、チームとしての関係性を深める工夫をしています。
── 採用においてもカルチャーフィットを重視されているとのことですが、具体的にはどのようにフィルターをかけているのでしょうか?
一次面接・二次面接の段階で、まずは各部門のリーダーが技術力やカルチャーの適合度をしっかりと確認します。そして、最終面接では代表の井崎がすべての候補者と面談し、SecureNaviの価値観や事業への共感度を丁寧に見極めています。その結果として、事業内容や組織文化に強く共感し、自走できる方が自然と集まってきている実感があります。
今後の目標・採用
── SecureNaviとしての今後の目標をお聞かせください。
目標として掲げているのは、SecureNaviのミッションでもある「セキュリティに取り組めば、売上が上がる世界をつくる」ということです。これは、私自身が過去に複数の企業でCTOやVPoEを務める中で、何度も直面してきた課題でもあります。
セキュリティというのは、どうしても「コスト」として見られがちです。たとえ重要性が理解されていたとしても、コストという視点になると稟議が通らなかったり、後回しにされてしまう。けれど本来は、セキュリティにしっかりと取り組むことで顧客や取引先からの信頼が得られ、結果的に売上やビジネス拡大にもつながるはずです。
だからこそまずは、私たち自身がそれを体現することが大切だと考えています。自社でしっかりセキュリティを実装・運用し、プロダクトとしてもそれを証明する。その結果、「セキュリティに力を入れている会社=ビジネスでも成功する会社」という認識を社会全体に広げていきたいと思っています。
── その目標に向けて、どのような技術戦略を描いているのでしょうか?
大きく3つの柱を設けています。
1つ目は「セキュリティファースト」という考え方です。業界標準を上回るセキュリティ水準を社内に浸透させ、外部にも示していく。その信頼が、やがて受注や売上につながることを実証していきたいと考えています。
2つ目は「AI共創」です。もはや「AIを使うかどうか」ではなく、AIと人がどのように融合し、新たな価値を創出するかが問われる時代です。AIエージェントとともに働く感覚を前提に、プロダクトへの組み込みや開発プロセス全体でAIを活用し、生産性と創造性の両立を目指しています。
3つ目は「セキュリティプラットフォーム構想」です。セキュリティを中心に据えた経済圏を構築していく、いわばセキュリティのインフラ企業になるというビジョンです。SecureNaviを基点に、周辺のシステムやプロダクトと連携し、より包括的なセキュリティ価値を提供していく予定です。
── その実現に向けて、どういった方と一緒に働きたいと考えていますか?
一言で言うと、志の高い方ですね。
特にスタートアップフェーズでは、うまくいかないことも多いです。そんなときに「自分は何ができるか」を前向きに考えて動ける人、周囲に良い影響を与えてチームを前進させてくれるような人と働きたいです。
技術力ももちろん重要ですが、志や熱量を持っている人のほうが、困難な状況を乗り越える強さを持っていると思います。実際にそういった人がいるだけで、チーム全体が前向きに動ける。だからこそ、「カルチャーフィット」や「志の高さ」は、スキル以上に重視しているポイントです。