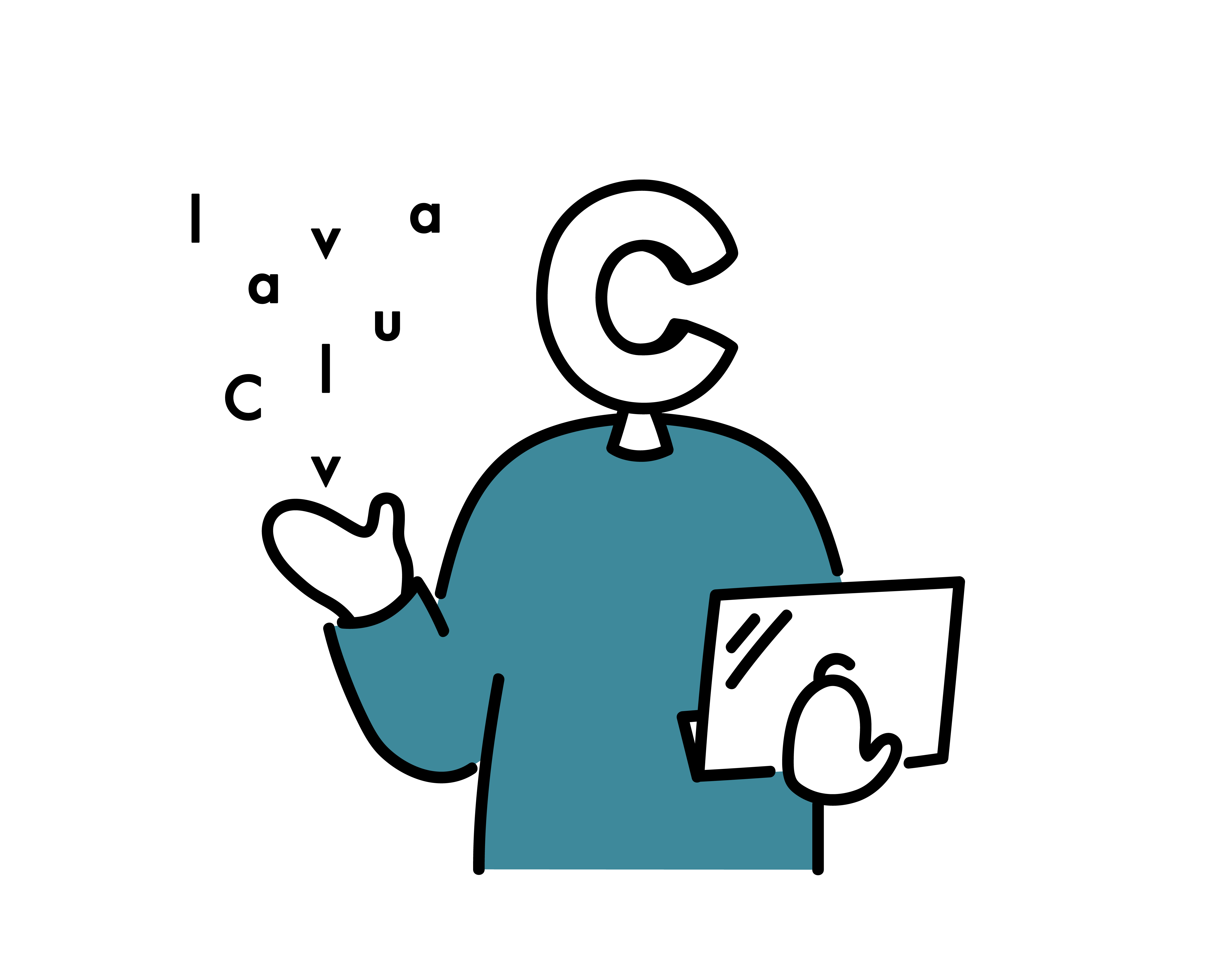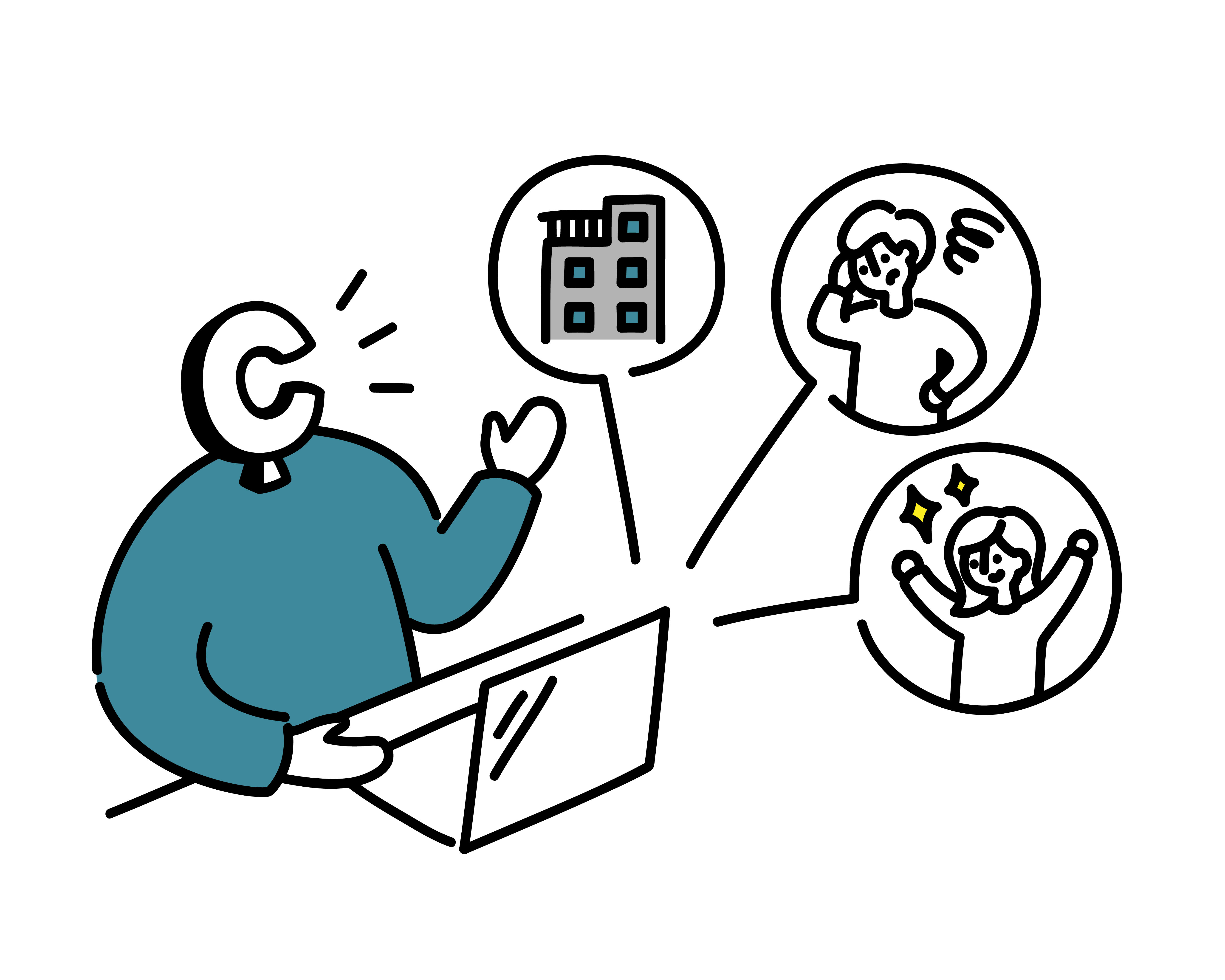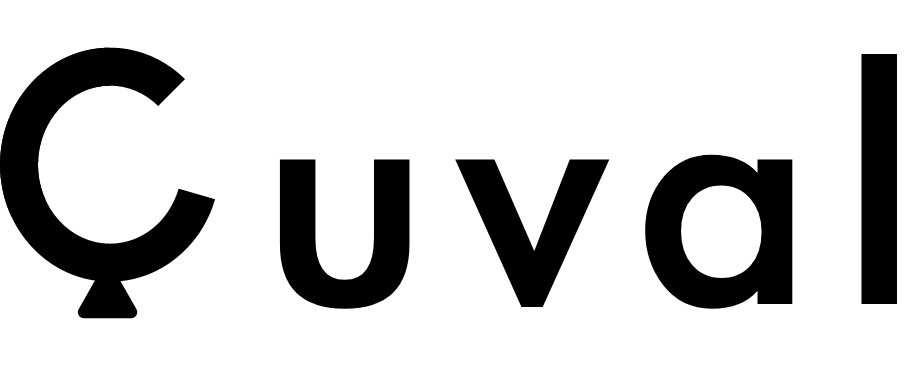得永 義則氏|教育DXコンサルタント/ICT戦略アドバイザー
IT黎明期にTISへ入社し、製造業の業務改善・ICT活用に従事。その後、金沢工業大学、関西大学、関西国際大学にて教育のDX推進を担い、ネットワーク整備からeラーニング導入、ポートフォリオによる学修成果の可視化など先進的な取り組みを主導。
現在はフリーランスとして大学法人や民間企業などのICT支援を行う。専門は教育の質保証/DX設計/プロジェクトマネジメント。2040年に向けた教育基盤の再構築と、企業・自治体における本質的な変革の伴走者として、現役で挑戦を続けている。
得永さんのキャリアについて
── まずはキャリアの出発点について伺います。学生時代から、新卒で東洋情報システム(現TIS)に入社されるまでの経緯を教えてください。
学生時代は電気工学科に所属していました。当時はまだ「情報工学科」という学科はなく、キャンパスに設置されていた大型コンピュータに触れる機会がありました。それが非常に面白く、「これからはこの世界が必ず来る」と強い興味を抱いたのを覚えています。今から55年ほど前のことです。
就職活動の際も、まだIT企業らしい会社はほとんどなく、ソフトウェアや情報処理関連の会社は数えるほど。ハードウェアではIBMやUNIVACなど外資系メーカー、ソフトウェアではCSKの前身や住友系、三菱系が出始めた頃でした。そんな中で私が選んだのは、60社が出資して立ち上げられたばかりの「東洋情報システム(TIS)」です。入社2期生というタイミングで、まさに会社づくりの過渡期に参画できることに魅力を感じ、「この会社と未来をつくっていきたい」と思い飛び込みました。
── 東洋情報システムでは、最終的に金沢支社長も務められましたが、入社後のキャリアの始まりはどのようなものだったのでしょう?
最初は、日本に初めて導入された大型コンピュータ「IBM System/370 Model 168」の運用管理を担当しました。その後、営業職へ転身し、金沢営業所に配属。石川・富山・福井の3県を担当しました。
北陸は製造業が盛んな地域で、当初は中小製造業向けに「コンピュータで業務効率をどう高めるか」を支援していました。やがて設計部門に特化する方向へシフトし、2D・3DのCADソリューションを提案。上場企業の大規模工場にも関与しながら、CAD活用による業務革新に尽力しました。
その後、本社で商品開発部や営業部の次長を務め、再び金沢に戻って40代で支社長に就任。TISでは13年ほどマネジメントを経験しました。
── 支社長としての立場は、現場の営業時代と大きく異なりましたか?
営業所長や支社長は、いわば「経営者」です。数字を追い、結果を出すプレッシャーは非常に大きかったですね。大学に転職した後、家族に「お父さんの顔が変わった」と言われたこともありました。数字に追われる仕事は、知らず知らずのうちにとげとげしさを生むのだと思います。
── そこから大学業界、金沢工業大学へ転職された経緯を教えてください。
よく訪問していた情報処理サービスセンター所長(理事)を務める教授から「うちに来てくれないか」と声をかけていただいたのがきっかけです。大学に行けば給与は下がると分かっていましたし、すぐには決断できませんでしたが、最終的に転職を選びました。理由は「転勤がない」「数字に追われない」「ICTリーダーとして旗を振れる」環境に魅力を感じたからです。
── 大学側にはどのような課題があったのでしょう?
大学が独自に開発した基幹システム(教務・学籍など)を外販するため会社を設立し、システム部門の人材がそちらに流れてしまったのです。その結果、教育・研究の視点でICTを舵取りする人材が大学内にいなくなっていた。たまたま毎年相当規模の案件で関わっていた私が顔を出していたことから、「得永さん、来てくれませんか」と招聘につながりました。
── 大学での取り組みの中で、特に印象深いものはありますか?
まず取り組んだのはインフラ整備です。当時は旧式の「10BASE2(イエローケーブル)」を使っており、インターネットもTSO(タイム・シャアリング・オプション)による限定的なものでした。その後、ATM(非同期転送モード)という高速規格を導入し、全国の大学で展開が進みました。
通信インフラが整った後は「教育にどう活かすか」という段階に進み、eラーニングを導入しました。当時はZoomのような双方向型ではなく、CAI教材を視聴するスタイルで、1本あたり50〜500万円もかかる時代。そこで学生アルバイトを教材開発に巻き込み、コストを抑えつつ質を高める仕組みをつくりました。全国的にも先進的な取り組みでした。
さらに、ポートフォリオシステムを日本の大学で初めて全学導入。学生の学びを可視化し、PDCAを回す教育改革を推進しました。2010年にはこのシステムで特許も取得しています。
── その後、関西大学、関西国際大学へとキャリアが続きますね。
関西大学への転職は、娘が入学したことがきっかけでした。保護者会の役員として関わっていた際に理事長と合宿でご一緒し、教育ICTの大規模プロジェクトを任せていただけることになったんです。約5年間当該プロジェクトに携わり、定年後も延長勤務しました。その後、自分がやりたいことに集中するため、以前から面識のあった関西国際大学の学長に相談し「ぜひ来てほしい」と言っていただき転職しました。
69歳からの新たな挑戦
── 2022年からはフリーランスに転向されています。決断の背景を教えてください。
69歳のとき、「まだ仕事がしたい」「教育の質保証にもっと本質的に関わりたい」と強く思ったのです。ただ最初はすぐに案件があるわけではなく、アルバイトや人材サービス会社経由の仕事でつないでいました。2年前からは総合大学のDX推進やベンダーの商品企画、民間企業のシステム導入支援などに関わる形で、再び自分の経験を活かせるステージに立っています。
── 実際、フリーランスとしての手応えはいかがですか?
難しいですね。教育の質保証については、どうしても私の思いが先走ってしまうことが多く、共感してもらえないこともあります。ただ、2040年には全国の大学の3分の2が淘汰されるとも言われています。だからこそ今、「教育のブランドづくり」や「学びの成果の可視化」に本気で取り組まなければならない。その思いは講演などでも必ず伝えるようにしています。
ハード/ソフト面に関する質問
── 得永さんの“仕事以外”のご趣味やご関心についても伺いたいのですが。
テーマパークが大好きなんです。特にディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)。実は今の自宅がユニバのすぐそばで、年パスを持っていた頃は「毎日でも行ける」という環境で通っていました(笑)。非日常の空間に身を置くのがとても好きなんです。
昔、TIS時代に金沢勤務の頃でも、会議で東京に出張した帰りに、わざわざ舞浜に寄ってディズニーランドに立ち寄り、最終の新幹線に飛び乗って帰る──そんなこともしていました。
── そこまで惹かれる理由は何でしょう?
やっぱり「異次元の世界に飛び込む感覚」ですね。現実から少し離れて華やかな空間に身を置く。それが癒しであり、活力でもある。最近では「ジャングリア」にも興味がありますし、毎月DX支援のために通っている長崎では、ハウステンボスにもよく立ち寄っています。
── ご家族での旅行も多いと伺いました。
はい。家族も旅行好きで、テーマパークも大好きです。TIS時代には「情報処理技術者」に加え「旅行業務取扱主任者」の資格を取ったほど、旅や非日常体験には惹かれてきました。
── 一方で、業務面での関心や専門分野についても教えてください。
ベースにあるのは教育分野ですが、それに限らず製造業や中小企業のDX支援にも関心があります。TIS時代から製造業の業務改善にITをどう活かすかを考えてきましたので、その延長線上に今もいる感覚です。最近も製造業からの相談をいただくことがありますし、企業規模に関係なく、プロジェクトの構想設計やロードマップづくりなど“絵を描く”ところを担うのは得意です。ベンダーコントロールの経験も長いので、現場の動かし方も含めて伴走できます。
── DXコンサルタントとして日々触れている技術分野は?
正直、新しい技術に対する高揚感はあまりありません。言語やツールは手段に過ぎませんから。ただ、生成AIには注目しています。とはいえ現時点では「いい加減な部分」も多い。だからこそ、それを支えるデータベースの設計・統合が非常に重要だと思っています。表面的な技術より「基盤となる構造」への関心が強いですね。
── セキュリティ分野についてはどうでしょう。
そこは高度に専門化された領域なので、私は専門家に任せます。基本的な知識は押さえていますが、深い防御設計まではできません。適切な人に委ね、全体をまとめるのが私の役割です。リケーションなどには関心がありますね。
── プロジェクト推進で特に意識していることは?
何より「人間関係」「コミュニケーション」です。50年近く働いてきて、結局ここが最大のテーマだと感じています。人は誰でも“我”を持っていて、それをどうまとめるかが難しい。相手の話をよく聞くのは大前提ですが、いくら耳を傾けても見えている世界が違えば納得してもらえないこともあります。
うまくかみ合えばチームは強くなりますが、対話が苦手な人ばかりだと、スキルが高くても苦しくなる。私は「さらけ出す」ことが一番だと思っています。偉そうにせず、「私はこういう人間です。一緒にやりませんか?」とありのままに向き合う。若い頃は偉そうにして失敗しましたが、繰り返す中で“自分が降りない限り、チームはついてこない”と気づきました。
── フリーランスとして参画する際、現場の文化はどうキャッチアップしているのですか?
一番は「キャッチボール」、密な対話です。特に“トップ”と話すことが多いですね。トップの言葉が中間で変換され、末端に伝わるときに意味が歪むことがあるからです。だからまず全体俯瞰が必要。今どこにいて何を変えるべきかを見極め、波風を予測して先手を打つようにしています。
── プロジェクトの規模感についても教えてください。
最近は数人〜十数人の小規模が多いです。最大は関西大学のプロジェクトで、私の直下に40〜50人、全体で100人以上が動いていました。
── やりがいを感じるのはどんなときですか?
「自分の仕事に夢を持っている人たち」と働けるときですね。やらされ感ではなく、夢を描けるメンバーと一緒に動くことが一番面白いです。
── 今後、注力したい分野や業界について教えてください。
教育の質保証は軸として続けます。日本の大学は厳しい局面にあり、大学淘汰の時代が訪れようとしています。学生に質の高い教育を届けることが問われている。これは海外にも広げるべきで、学位やCertificateを国際的に発行する仕組みづくりに挑戦したい。アメリカではOPM(オープンプログラムマネジメント)が定着していますが、日本はまだまだ。ここに挑む意欲があります。
一方で、中小企業のDX支援もやりたい。特に従業員100人未満の企業は変革しやすく、支援の効果が大きい。また、自治体DXも重要です。以前ある県のCIOに応募し最終選考まで進んだ経験もあり、行政こそ変革が必要だと痛感しました。ガバメントクラウドやスーパーアプリ、スマートシティ、MaaSなどを有機的に連携・活用すれば、もっと住民に寄り添えるはずです。命を削る覚悟で取り組む必要がありますが、面白い挑戦だと思っています。
PR・今後について
── ご自身の強みを一言で表すと?
「チャレンジを支える力」です。企業の強み・弱みを整理し、市場を見据えてDXのステップを描く。日本経営品質賞(JQA)のセルフアセッサーとしての経験もあるので、客観的に企業を分析しながら伴走できます。
── 関わる企業の規模感としては?
やはり100人未満の中小企業が一番変わりやすい。ただ、規模に関係なく「変わりたい」という意志がある組織であれば、全力で支援します。
── 最後に、今後の目標をお聞かせください。
これまで総務省や文科省の施策にも応募してきました。総務省の「変な人募集」という枠にも応募したことがあります。数百万円の予算を使って地域や業界に新しい風を吹き込む取り組みです。私が一貫して提案してきたのは、日本の教育の質保証のための「仕組みづくり」。その仕組みが機能すれば、教育の力が国の力になると信じています。
だからこれからも「手を挙げてくれる企業」と一緒に、“夢を追いかける”仕事をしたい。チャレンジングな仲間と未来を設計できたら嬉しいですね。