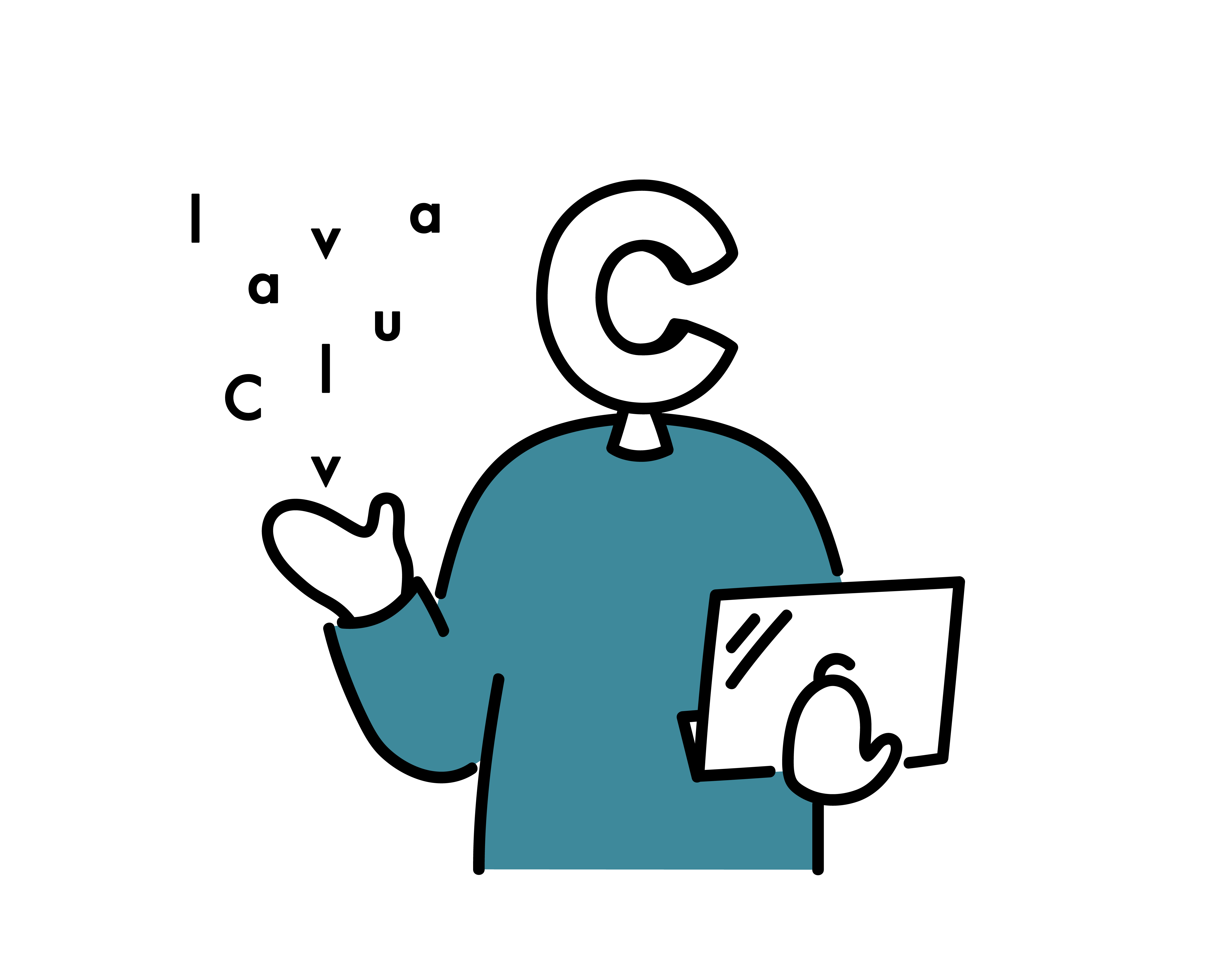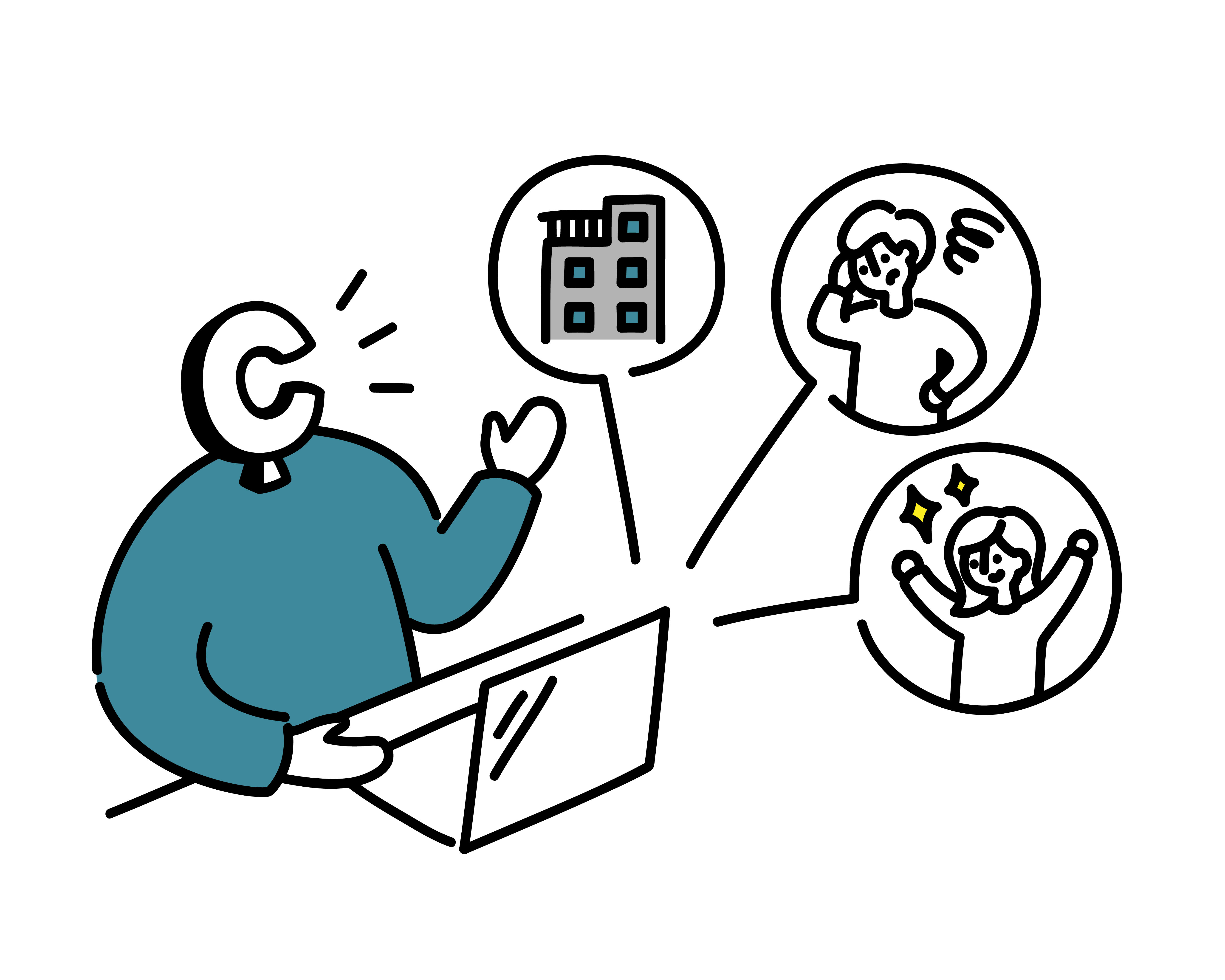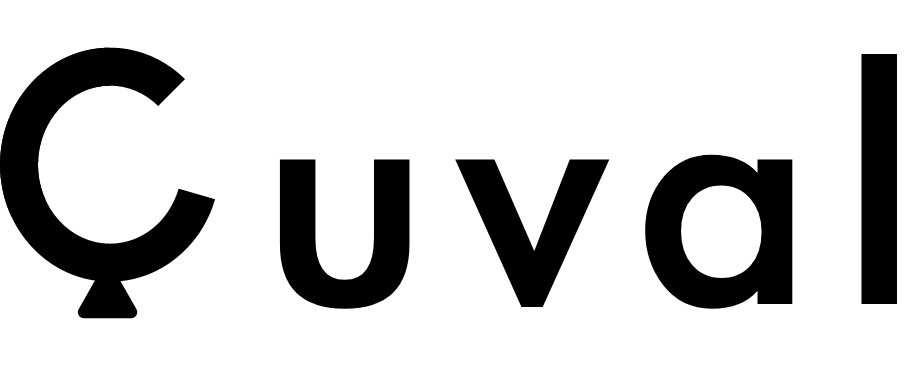和田 豊 氏|千葉工業大学 教授/AstroX株式会社 CTO。
東海大学でハイブリッドロケット開発に携わり、大学院ではJAXA宇宙科学研究所にて推進系研究に従事。秋田大学助教として能代宇宙イベント運営と発展に関与し、現職では「ロックーン(気球からの空中発射)方式」を軸とした宇宙輸送技術の社会実装に取り組む。研究とスタートアップ開発の両面から、宇宙・成層圏という未踏領域の開拓を進めている。
AstroX株式会社について
── 御社の事業内容を教えて下さい。
AstroXは、「宇宙輸送」に特化したスタートアップです。人工衛星を宇宙空間へ届ける手段を開発・提供する企業であり、現在、創業から5月で4期目を迎えました。
この分野には、インターステラテクノロジズやスペースワンなど、すでに実績を築いている企業も存在していますが、私たちはそうした先行企業とはまったく異なるアプローチで挑戦しています。
AstroXが取り組んでいるのは、「ロックーン(気球からの空中発射)方式」という新しいロケット打ち上げのスタイルです。これは、気球を使ってロケットを成層圏(高度20〜30km)まで運び、そこから空中発射して人工衛星を宇宙に届けるという技術。実用化された例はまだ世界になく、私たちはこの“未踏の領域”に真正面から挑んでいます。
この方式には、主に3つの大きなメリットがあります。
まず1つ目は、通常最も難易度が高いとされる「1段目ロケットの開発」が不要になる点です。ロケットの1段目は、大推力が要求され、構造も非常に複雑で、膨大なコストと技術力が求められる領域。多くの開発がこの“死の谷”で止まってしまう中、私たちは気球の浮力を活用することでこのステップ自体をスキップできるという発想で進めています。
2つ目は、エネルギー効率の高さです。気球で空気の薄い成層圏まで運んでから発射することで、空気抵抗が大幅に軽減され、エネルギーロスも抑えられます。これにより、小型ロケットでも十分な質量の衛星を軌道投入可能になり、、小型故に高頻度での打ち上げも現実的になります。
そして3つ目は、日本の地理的制約を乗り越えられる点です。日本は東西南北を海に囲まれ特に東と南が開けていることから、理論上は打ち上げに適した地形に見えますが、実際には沿岸部にも多くの生活圏が存在し、航空機や商船の航路や漁業活動との調整が必要であり、地上からの打ち上げの高頻度化は極めて困難です。そこで私たちは、“空”からの発射という新たな選択肢を開くことで、日本発の宇宙輸送をもっと自由に、もっと加速させたいと考えています。
そして私たちが目指すのは、宇宙だけではありません。ロケット以外の重量物を成層圏へと安全に運べる気球技術を活用し、この“空白地帯”とも呼べる高度20〜30kmの成層圏を、人類の新たな活動拠点として開拓する──そんな未来も視野に入れています。
「宇宙を目指す」ことと、「成層圏を活用する」こと。この2つの挑戦を同時に進めながら、AstroXはこれまでにない輸送インフラの実現に向けて、一歩ずつ歩みを進めています。
和田さんのキャリア

── ではキャリアについて、幼少期から高校時代までさかのぼってお話を伺えますか?現在の仕事にもつながる「ものづくり」への関心や原体験などがあれば、ぜひ教えてください。
実は、幼い頃の私は「ものづくりが大好きな子ども」だったわけではありませんでした。小学生の頃は、夢中になれるようなものが特になく、ただ毎日、友達と野原を駆け回るような活発で少し落ち着きのない子どもだったと思います。
そんな中で唯一、今でも記憶に残っているのが、父が購読していた科学雑誌『Newton』です。内容はほとんど理解できなかったのですが、「宇宙ってなんだかすごそう」「よくわからないけど、面白そう」という漠然としたワクワク感がありました。今思えば、それが“宇宙”に初めて触れた原体験だったかもしれません。
中学時代はソフトテニス部にどっぷりとハマり、毎日テニスばかり。高校はその延長で、テニス強豪校の東海大学付属相模高等学校に進学しました。高校でもテニス漬けの毎日で、インターハイに出場することもできましたが、いわゆる“勉強漬け”とは無縁の高校生活でした。
高校3年の夏が終わり、「さて、進路をどうしようか」と考えたとき、他大学を受験するという選択肢は現実的ではありませんでした。附属校だったこともあり、そのまま東海大学への内部進学を選ぶ流れに。進学先を検討する中で、たまたま目に入ったのが「航空宇宙学科」の文字でした。
「宇宙について学べるのか?」と目が留まり、ふと、小学生のときに読んでいた『Newton』の記憶がよみがえったんです。「なんか面白そうだな」と思い、その直感を信じて進学先を決めました。このときの選択が、今のキャリアにつながる最初の一歩でした。
── では、大学に進学されてからは、どのようなことを学ばれていたのでしょうか?
東海大学の航空宇宙学科に進学して、最初の大きな転機になったのが「学生ロケットプロジェクト」との出会いでした。
このプロジェクトでは、NASAが提供する固体ロケットに観測機器を搭載し、アラスカ大学と共同で打ち上げ実験を行うというもの。最初は「なんとなく面白そうだな」という軽い気持ちで参加したのですが、アメリカの学生たちと一緒にものづくりを進めるという経験は、とても新鮮で刺激的でした。
ただ、このプロジェクトは4〜5年に一度しか打ち上げのチャンスがない大規模なものだったため、次第に「もっと頻繁にロケットを打ち上げたい」「自分たちで開発できないか」と思うようになったんです。
その思いをアラスカ大学の学生に話したところ、「ハイブリッドロケット」という比較的安全で構造がシンプルなロケットがあると教えてもらいました。そこから一気にのめり込み、学部時代はハイブリッドロケットの開発に没頭していきました。
そして学部4年のとき、北海道・大樹町で、大学生としては日本で初めてとなるハイブリッドロケットの打ち上げにも成功しました。このときの体験は、今でも自分の原点として、心に残っています。
── その後、総合研究大学院大学へと進まれていますが、なぜその大学院を選ばれたのでしょうか?
総合研究大学院大学、通称「総研大」は、国内の国立研究所に大学院生を派遣する目的で設立された大学院です。私が進学を決めたのも、JAXAの宇宙科学研究所(ISAS)に学生が派遣される制度があることを知ったのがきっかけでした。
もともと私は、東海大学の修士課程で共同利用研究員制度を利用してISASで推進系を専門とされていた堀先生のもとで研究を行っていたのですが、その研究が本当に面白くて。「もっと深く突き詰めたい」と感じ、博士課程に進もうと決めたんです。
ただ、進学を考えていたタイミングで、東海大学での受け入れ教員である先生が定年退職されることになりまして。新たに研究を継続できる環境を探す中で、総研大からISASに派遣される進路を見つけた、という経緯があります。
また、総研大は国立大学ということもあり、学費面での負担が軽く済む点も魅力でした。何より、修士課程で取り組んでいた研究テーマをそのまま引き継げるというのが非常に大きかったですね。
なので、「大学を変えた」というよりも、“研究を継続するために最適なフィールドを選んだ”という感覚に近いです。
── その後、大学院を修了されて秋田大学の助教になられたと思いますが、そこに至るまでの経緯について教えていただけますか?
先ほども少し触れましたが、学部4年生のときに北海道・大樹町で、日本の大学生としては初めてハイブリッドロケットの打ち上げを行った経験があります。ただ、この大樹町という場所は、冬季にしか打ち上げができない地域でした。というのも、打ち上げ場所として使っていたのが牧草地で、雪に覆われている冬季限定でしか使用許可が出なかったんです。
「じゃあ、次は夏にも打ち上げたい」と思うようになり(笑)、そのときにご縁があったのが、当時秋田大学の助教だった秋山先生でした(のちに和歌山大学の教授を務められます)。「夏でもロケットの打ち上げができる場所はありませんか?」と相談したところ、「秋田県の能代市なら広く開けた場所がある」と教えていただきました。
その出会いがきっかけとなって、翌年から「能代宇宙イベント」という学生主体の宇宙開発イベントがスタートします。2024年には第20回を迎え、今では全国から500〜600人の学生が集まり、ロケットや人工衛星の共同実験を行う一大イベントに成長しています。
私自身、その記念すべき第1回に東海大学の学生として参加し、秋山先生の支援を受けながらロケットを打ち上げました。この経験は、自分の中でも非常に大きな原体験になりました。
その数年後、秋山先生が和歌山大学に異動されることになり、秋田大学でのポジションが空くタイミングと、私が博士課程を修了する時期が重なったんです。そのとき、秋田大学から「教員として、学生たちのロケットプロジェクトを支援してみないか」と声をかけていただきました。
学生として参加した場所に、今度は教員として戻ってくる──この流れは、とても感慨深かったですし、自分のキャリアの中でも節目となる出来事でした。これが、秋田大学での教員としてのキャリアのスタートでした。
── その後、秋田大学から千葉工業大学へと異動されたと思いますが、どういった経緯だったのでしょうか?
秋田大学では、地元企業と連携して観測ロケットを開発・打ち上げるプロジェクトに取り組んでいました。そんな折、千葉工業大学の松井先生(故人・元学長)から「千葉工大でも観測ロケットの開発を本格化させたい。中心を担ってくれないか」とお声がけいただいたのが転機でした。
ちょうどその頃、私の秋田大学でのポジションは任期付きで再任不可の契約だったため、「次のステージを考えなければ」という時期でもあったんです。ご縁とタイミングがうまく重なった結果、千葉工業大学への異動を決意しました。
しかもそのとき、ちょうど「機械電子創成工学科」という新学科の立ち上げ準備が始まるタイミングでもあり、1年目は「惑星探査研究センター」で研究に取り組みつつ、新学科の設立にも携わることができました。
その翌年からは、准教授として機械電子創成工学科に所属し、今もなお、教育と研究の両面で活動を続けています。
── AstroXで取り組まれている「ロックーン方式」ですが、その技術の原点となるような経験があったと伺いました。詳しく教えていただけますか?
AstroXで現在取り組んでいる「ロックーン(気球からの空中発射)方式」の技術には、私自身の過去の研究経験が深く関わっています。
以前、山口県の助成金を活用したプロジェクトがあり、県内の航空宇宙クラスターと東京のベンチャー企業が共同で空中発射技術の実証に挑戦していた時期がありました。当時、「空中発射に挑戦したいが、何から手を付ければ良いのか分からない」といった状況の中で、技術の分かる研究者を探していた関係者の方から私に声がかかったんです。
ちょうどその頃、私は洋上発射の研究にも取り組んでいました。というのも、日本のように地理的・人口密度的に制約の多い国では、ロケットの地上発射には限界があります。ですから、「洋上」「空中」といった“可動型の打ち上げ手段”を視野に入れた研究を進めていました。
「洋上をやっているなら、空中もやるべきだ」という流れの中で、そのプロジェクトに参加することになったのが、空中発射との本格的な関わりの始まりでした。
── AstroXに正式に参画された経緯について伺えますか?小田さんとの出会いや、意思決定に至るまでの流れについても教えてください。
山口県のプロジェクトでは、約3年間にわたり空中発射の基礎技術を確立する研究を進めていました。さらにその先の実用化に向けて、NEDOの予算も獲得していたのですが、思いもよらぬ不幸が起こりました。一緒に研究を進めていたベンチャー企業の中心人物が急逝し、NEDOのプロジェクトも1年目の途中で打ち切られてしまったんです。技術はあるのに、それを社会に届けるための道が途絶えてしまったような状況でした。
そんなとき、転機となったのがSPACE COTANという企業に所属していた大出さんとの再会です。彼は元・大林組のエンジニアで、私が洋上発射の研究をしていた際の共同研究パートナーでもありました。能代宇宙イベントの話なども共有していたことから、宇宙産業に強い興味を持ち、のちにSPACE COTANへ転職された方です。現在は独立して「ASTROGATE」という会社を立ち上げられています。
その大出さんが立ち上げたYouTubeチャンネルで、動画を公開しているのですが、それを偶然視聴されたのがAstroX代表の小田でした。
小田はもともと宇宙に強い興味を持っていたものの、技術的なバックグラウンドはなく、どちらかといえば経営畑の人間です。過去に複数の企業を成功させた実績と、一定の資金力もあり、「技術パートナーさえいれば、自分も宇宙事業に挑戦できるのではないか」と考えていたタイミングだったようです。
そこで小田が大出さんに「誰か信頼できる技術者を紹介してほしい」と相談したところ、「それなら和田先生しかいない」とご紹介いただき、私と小田の出会いが実現しました。
初めてお会いしたとき、私は「空中発射の技術的な基盤はすでにできている。ただ、それを社会に実装していくには経営と資金調達の力が必要だ」とお話ししました。小田も「後発のスタートアップが成功するためには、誰もやっていない新しいアプローチが必要だ。空中発射はその核になり得る」と共感してくださって。
そこからは一気に話が進み、「この技術を軸にした会社を立ち上げよう」と意気投合し、AstroXの創業に至りました。私は創業メンバーとして参画し、現在はCTOとして技術の推進と社会実装を担っています。一方で、小田は経営全般と資金調達を担うという、非常に明確な役割分担で事業を進めています。
── なるほど。創業はいつ頃だったのでしょうか?
小田と初めてお会いしたのが、2020年の12月頃です。そこから翌年にかけて起業準備を進め、AstroXは2022年5月に正式に設立されました。現在で、ちょうど創業4期目に入ったところです。
AstroX 参画後
── 創業から一緒に立ち上げを担われたかたちだと思いますが、まずは創業後、どのような取り組みからスタートされたのでしょうか?
空中発射に必要な基礎技術は、創業以前から一定の実証が進んでいました。ただし、それはあくまで小規模なレベルに留まっていたため、AstroXの創業後にまず着手したのは、この技術を“宇宙”とされる高度100kmに届くスケールにまで引き上げることでした。
具体的には、ロケットエンジンの燃焼実験をはじめ、発射の向きを制御するための姿勢制御装置の開発、そしてロケットを成層圏まで運ぶ気球の調達と運用体制の整備など、要素技術の拡張と大型化に段階的に取り組んでいきました。
最終的なゴールは「空中からロケットを打ち上げて宇宙空間(高度100km)へ到達させること」ですが、それに至るまでの道のりとして、まずは地上からロケットを打ち上げ、その性能と安全性を確かめる段階も経ています。実証と検証を重ねながら、確実に次のステップへと技術を進めているフェーズです。
── ちなみに、最初は「技術顧問」という立場で関わられていたという認識でよろしいですか?
はい、そのとおりです。AstroXの創業初期は、まだ社員を雇う段階ではなく、研究フェーズに重点を置いた体制でした。業務委託を中心にしながら、まずは中高度帯(宇宙手前)を目指したロケット開発を社外ベースで進めていたんです。
私自身も当時は大学の研究室の運営が本業でしたので、AstroXへの関わり方としては、あくまで研究活動の延長線上。技術的なアドバイザーとしてサポートしており、「技術顧問」という肩書きでの関与からスタートしました。
── なるほど。そこから現在のCTOに就任されるに至った経緯についても教えてください。
転機となったのは、昨年の春ごろ(2024年3月頃)です。技術開発がある程度進み、「本格的にこの技術で宇宙を目指すフェーズに突入した」と判断したタイミングでした。
それに伴い、AstroXとしても正社員の採用を本格的に開始し、組織体制や開発スピード、品質管理、技術連携などをより高いレベルで整えていく必要が出てきました。そうした状況の中で、「顧問」という立場のままでは限界があると感じ、経営の意思決定にも深く関わる役割が必要だという判断に至りました。
── 実際にCTOとして本格的に関わるようになってから、大学での研究との違いや、苦労されたこと・逆に良かったことなどはありましたか?
そうですね。大学での研究は、基本的に原理原則に則って一歩ずつ積み上げていく世界です。教育機関でもあるため、学生に「自分で考え、手を動かし、得られた結果を考察し、まとめる」というプロセスを経験させることも大切です。進行スピードも基本的には1年単位で、学生の成長に合わせて研究成果を出していくという、長期的な視点での取り組みになります。
それに対して、AstroXでCTOを務めるようになってからは、まったく異なる環境に身を置くことになりました。今は、“一刻も早く技術を社会に出して実績をつくる”ことが最大の使命です。学生の成長を待つのではなく、すでに高い専門性を持ったプロフェッショナルたちをどう効率的に活かしていくかが問われます。
時間、コスト、安全性──そのすべてをバランスさせながら、スピード感をもって意思決定をしなければなりません。大学の“育てる研究”から、スタートアップでの“動かす開発”へ。最初はマインドセットの切り替えに戸惑いもありましたが、非常に刺激的でしたし、新しい視点で技術と向き合えることに大きな面白さを感じています。
── よく「大学の先生と経営者の連携は難しい」という声も聞きます。AstroXでは和田さんと小田さんがうまく連携されている印象がありますが、その秘訣があれば教えてください。
確かに、研究者と経営者では役割や価値観も異なるので、うまく連携を取るのが難しいケースもあると聞きます。私自身も長く大学で研究をしてきた人間ですから、「会社」という枠組みの中で組織をどうつくり、どうスケールさせるかといった知見はまったくありませんでした。
それに、企業運営では“資金”の確保が極めて重要になります。予算の調達、補助金の活用、ベンチャーキャピタルとの交渉──こうしたことは、大学教員のキャリアの中ではほとんど経験しない領域です。
その部分をすべて支えてくれたのが、CEOの小田です。彼はこれまでに複数の会社を立ち上げ、経営者としてさまざまな修羅場をくぐってきた方。資金調達、ピッチイベントでの発信、行政との連携など、スタートアップに必要なスキルをすべて持っている人物です。
おかげで私は、技術と開発に専念できる環境を整えてもらいました。大学での研究費は、基本的に人件費を含まないものが多いのですが、スタートアップではエンジニアの人件費を含めて予算を組み、資金を確保しなければなりません。そのための計画や申請も、私にとっては未知の世界でした。
結果として、私たちは非常に明確な役割分担のもとで動いています。小田が「会社に必要な資金と人材を集める」役割を担い、私が「会社に必要な技術と技術力を提供する」役割を担う。お互いがその領域で信頼し合っているからこそ、AstroXというチームが今のようにうまく機能しているのだと思います。
── 現在、CTOとしてどのような業務を担当されていますか?
現在、AstroXではCTOとして、全社の技術戦略を統括しながら、経営にも深く関わる役割を担っています。
社内には、ロケット、姿勢制御装置、気球、そして制御・通信を担うコントロールシステムという、4つの専門的な技術グループが存在しています。私はそれぞれのグループの進捗を把握し、技術的な相談や意思決定のハブとして機能しながら、「次に何をすべきか」という戦略を描き、実行に移すところまでをリードしています。
単なる技術の監修にとどまらず、その戦略を実現するためのストーリー設計や、必要なリソース・体制の整備までを見据え、開発計画全体の“地図”を描いていくことも、私の重要な役割のひとつです。
── 改めて、AstroXの事業の魅力についてもお聞かせください。
最大の魅力は、「人類がまだ誰も成し遂げていない技術」に真正面から挑戦していることにあります。
私たちが開発している「ロックーン(気球からの空中発射)方式」は、世界中でもまだ誰一人として実用化に成功していない技術です。つまり、“正解のない問い”に、自分たちの知識と技術、経験を総動員して挑んでいる。そのプロセス自体が技術者として非常にやりがいのあるものであり、自分たちの手で未来の“正解”をつくっていくような感覚があります。
さらに私たちは、宇宙だけでなく、成層圏(高度20〜30km)という未開拓の領域にも挑戦しています。
気球によってロケットを成層圏まで運び、そこから打ち上げるという私たちの方式は、言い換えれば「重たいものを安全に成層圏へ輸送する」技術でもあります。そして、この成層圏というのは、地上でも宇宙でもない、人類にとっての“空白地帯”なんです。
この領域を活用できるようになれば、たとえば通信機器を設置して、人工衛星を介さない高速通信インフラを構築したり、太陽電池を浮かせて空中で発電する技術を実現できるかもしれません。
まるで「ラピュタ」のような空の世界が、いよいよ現実味を帯びてきているんです。
宇宙を目指しながら、同時に地球の“空の上”の使い方を根本から変える──。AstroXの事業には、そうした未来を切り拓く両面の可能性があると考えています。
現在の組織について
── 現時点での組織体制や、人数構成について教えてください。
現在AstroXには、正社員が約18名在籍しており、そのうち約15名がエンジニアです。さらに業務委託や外部パートナーも含めると、全体ではおよそ25〜26名の体制で活動しています。
私たちは、限られたリソースで多くの技術課題に挑むスタートアップだからこそ、開発体制を4つの専門グループに分けて運営しています。
1つ目は、ロケットそのものの開発を担う「ロケットチーム」。2つ目は、飛行中の姿勢や方向を制御する「姿勢制御装置チーム」。3つ目は、成層圏までロケットを運ぶための「気球チーム」。そして4つ目は、通信・地上設備・全体制御を担当する「コントロールチーム」です。
── 4つのチームはどのように連携しているのでしょうか?
開発の多くはチームごとに独立して進めていますが、打ち上げ実験や放球テストのような実地フェーズでは、グループを横断して必要なスキルを持ったメンバーが集まり、プロジェクトベースのチームを編成しています。
その連携を支えるため、私たちは「プロジェクトマネージャー(PM)」と「システムエンジニア(SE)」という2つの横断的な役割を設けています。PMは全体進行を管理し、SEは各技術要素のインターフェース調整や方向性の統合を担います。
「ロックーン」という統合型システムの開発を成功させるには、こうした機能的かつ柔軟な体制が欠かせないと実感しています。
── 現在、特に注力している開発テーマについて教えてください。
私たちは現在、福島県・南相馬、東京、千葉工業大学の3拠点で開発を進めています。
南相馬ではロケットの組み立てや実機検証を、東京では姿勢制御装置の設計・開発とコーポレート機能を、千葉工業大学ではロケット関連の基礎研究を担っています。
人数に対して拠点が分散しているため、チーム間のコミュニケーションは常に課題です。Slackなどのツールを活用したリアルタイム共有はもちろん、月に1度は全社員が東京に集まり、オフラインでの月例会を開催。意見交換や食事を通して、信頼関係を深める場としています。
── そうした体制の中で、AstroXの「強み」と「課題」をどのように捉えていますか?
一番の強みは、何より“チャレンジ精神に満ちたエンジニアが揃っている”ことです。
空中発射という分野は、世界的にも前例が少なく、知見も乏しい未踏の領域。小さな失敗を恐れず、一歩一歩前進し続ける粘り強さや探究心を持ったメンバーが、AstroXには集まっています。
また、大学側が保有する実験装置などを活用できる点も、スタートアップとしては大きなアドバンテージです。アカデミアと連携しながら、理論と実証の両輪で技術開発を進められる環境は、信頼性と開発スピードの両面で強みになっています。
一方で課題は、やはりリソースの不足です。やるべきことも、進むべき技術の道筋も明確に見えている──それでも、“人”と“時間”が足りない。だからこそ今後は、私たちのビジョンに共感し、一緒に挑戦してくれる仲間をどれだけ巻き込めるかが、組織としての最大のテーマになると思っています。
今後の目標・採用
── 今後の目標について、改めてお聞かせください。成層圏や宇宙といったキーワードが非常に印象的でした。
はい。直近の目標は、自社で開発したロケットを用いて、高度100kmの宇宙空間に到達させることです。これは今年度中、もしくは来年度の初頭までに達成したいと考えています。
この到達が実現すれば、私たちがこれまで取り組んできた「ロックーン(気球からの空中発射)方式」という打ち上げ技術が、単なる研究ではなく、実用に耐えうることを対外的に示すことができます。それは次の資金調達にもつながる、大きなステップになると考えています。
その先には、2028年〜2029年を目処に、人工衛星を軌道に投入するフェーズを見据えています。すでにそれに向けた、より大型のロケット開発にも着手しており、次世代の宇宙輸送を担うための技術基盤を築いているところです。
さらにその先には、ロケットの量産体制を整え、高頻度での打ち上げを可能にする仕組みづくり、そしてAstroXの強みである「気球技術」を活用して、ロケット以外の重量物も成層圏へ輸送できるインフラの構築を目指しています。
宇宙という最前線への挑戦はもちろん、地球と宇宙の間にある“成層圏”という未活用の高度領域を、新たな社会インフラとして活かす。その実現こそが、AstroXが描いている未来のビジョンです。
── 採用の観点では、今後どのような方と一緒に働いていきたいとお考えですか?
AstroXには、「人類がまだ成し遂げていないことを実現したい」という強い意思を持った仲間が集まっています。だからこそ、自分の技術で未踏の領域に挑みたい、未知の課題にワクワクできる。そんな“マインドを持った人”とご一緒したいと考えています。
宇宙産業は今後、日本国内でも8兆円規模の成長産業になるといわれていますが、現時点ではエンジニアの数が圧倒的に不足しています。もちろん、大学や教育機関での人材育成は重要ですが、それと同じくらい、今まさに他業界で活躍している方が“宇宙へ転身する”ことも、大きな希望です。
実際、AstroXでは、自動車業界や防衛産業出身のエンジニアが多数在籍し、第一線で活躍しています。「宇宙開発の経験がない」という理由で躊躇する必要はまったくありません。必要なのは、“挑戦する気持ち”だけです。
機械・電気・情報・制御・通信といった総合工学の知見が求められる分野なので、どんな専門性であっても、活躍できるフィールドがAstroXにはあります。むしろ、多様な視点とバックグラウンドが求められる世界だからこそ、一緒に新しい技術を形にしていける仲間を求めています。
そして、もうひとつ大切にしているのが「人柄」です。これはCEOの小田もよく言うのですが、「いいやつであること」。どんなに技術力が高くても、信頼し合える関係でないと、本当に強いチームはつくれません。共に挑戦できる“いい仲間”と、これからのAstroXをつくっていきたいと思っています。
── 最後に、読者の皆さんへメッセージをお願いします。
これは小田もよく話していることですが、私たちは本気で「日本の宇宙産業を世界一にしたい」と考えています。AstroXだけの挑戦ではなく、日本全体の産業を盛り上げ、世界に誇れる技術を届けていきたい。そのために日々取り組んでいます。
技術で世界を驚かせたい。日本発の技術で社会に新しい価値を届けたい。そんな未来に共感してくださる方がいれば、ぜひ一度AstroXにお越しください。きっと、わくわくするような挑戦が待っているはずです。